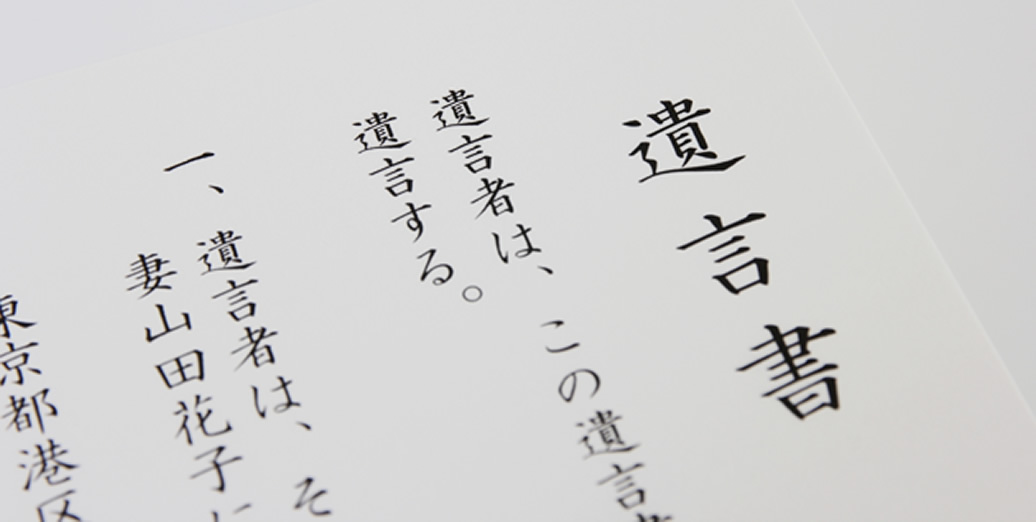
はじめに
今回も、事例ごとに遺言書を作成する際の注意点について解説していきます。
ケース1
Aには、全く身寄りがなく、Aが亡くなった場合に相続人となるべき者(以下「推定相続人」という。)もいない状況であった。そこで、Aは、自分自身が死亡した際には、幼馴染のBに対して、財産をあげたいと考えている。
検討と対策
そもそも、民法においては、法定相続人がいない場合には、相続人不存在であるとして、相続財産管理人を選任するなど一定の手続きを経た上で、最終的には、国庫に財産が帰属することになっています。
もっとも、遺言書において、特定の人(B)に対して、遺言者(A)自身が亡くなった際に、贈与する旨の記載をすることで(遺贈といいます。)、遺言者(A)自身が亡くなった際に、財産の所有権等を受贈者(B)に移転させることが可能です。
ただし、遺贈を受けた受贈者(B)は、遺言者(A)の死亡後、遺贈の放棄をすることができますので、場合によってはあらかじめ受贈者(B)の意思を確認しておくことをお勧めします。仮に、受贈者(B)が遺贈の放棄をすれば、ケース1の場合には、相続人不存在ですので、相続財産管理人を選任するなど一定の手続きを経た上で、最終的には、国庫に財産が帰属することになります。
ケース2
Aには、全く身寄りがなく、Aが亡くなった場合に相続人となるべき者(以下「推定相続人」という。)もいない状況であった。そこで、Aは自分自身が死亡した場合には、遺言により、自己の財産をどこかの団体等に寄付したいと考えている。もっとも、現時点では、寄付をする団体が決まっておらず、どうするべきか悩んでいた。そこで、誰に対して遺贈を行うかについては、第三者に判断を委ねることにしたいと考えた。
検討と対策
遺言には、遺言代理禁止の原則があり、これは、遺言者自身が、自分で遺言の内容を確定させ、遺言を作成する必要があり、他の人の意思による補充代理を許さないとする原則です。
もっとも、遺言の内容の一部を第三者に委ねることが一切許されないわけではなく、民法の規定においても明文で認められているものもあります(民法第902条第1項、同法第908条、同法1006条第1項など)。
そのため、誰に対して遺贈を行うか(受贈者の選定といいます。)についても、他の第三者に委ねることが可能となるかが問題となります。
この点、最高裁平成5年1月19日第三小法廷判決・民集47巻1号1頁では、受贈者の選定を遺言執行者(一般の第三者ではありません。)に委託することが可能であるか否かについて、「本件遺言は、・・・・その選定を遺言執行者に委託する内容を含むことになるが、遺言者にとって、このような遺言をする必要性のあることは否定できないところ、本件においては、遺産の利用目的が公益目的に限定されている上、被選定者の範囲も前記の団体等に限定され、そのいずれが受遺者として選定されても遺言者の意思と離れることはなく、したがって、選定者における選定権濫用の危険も認められないのであるから、本件遺言は、その効力を否定するいわれはないものというべきである。」と判示され、受贈者の選定を遺言執行者に委託することも可能であるとしています。しかし、この判例は、いわゆる事例判断ですので、すべての遺言執行者の事案において適用されるわけではないことや、遺言執行者ではない一般の第三者の場合にも妥当するのか、などについては考え方が分かれています。
そのため、遺言者自身(A)で受贈者を選定しておくことが望ましく、遺言執行者や第三者に委ねるのは、弁護士や公証人などに相談した上でやむを得ない場合にしましょう。
また、受贈者が、法人であれば問題はありませんが、社会には、団体としての実態を有していながら、法人格を有していない団体(多くの自治会・町内会・同窓会など)も存在します(法人格を有していないものの、権利能力なき社団と呼ばれる団体に該当する場合もあります)。加えて、遺贈を受けた受贈者は、遺言者の死亡後、遺贈の放棄をすることができます。
そのため、念のために、受贈者とする予定の団体に対して、法人格の有無や、遺贈を受ける意思があるのかについて、事前に確認することをお勧めします。









 0120-131-554
0120-131-554