
今回は、付言事項及びその効果・影響についてご説明します。
※本記事と関連する過去の記事
https://egonsouzoku.com/magazine/magazine-177/
https://egonsouzoku.com/magazine/magazine-218/
https://egonsouzoku.com/magazine/magazine-1084/
https://egonsouzoku.com/magazine/magazine-1134/
1 法定遺言事項
法定遺言事項とは、法的な効力が生じる事項として法律で定められた事項のことであり、具体的には、相続分の指定(民法第902条)、遺産分割方法の指定(民法第908条)、遺言執行者の指定(民法第1006条)、生命保険受取人の変更(保険法第44条)、認知(民法第781条第2項)等があり、遺言により法的な効力が発生します。
2 付言事項
付言事項とは、法定遺言事項と異なり、法的な効力が生じる事項として法律に定められていない
事項のことであり、感謝の意の表明、葬式の方法、献体、訓戒、家族間の融和に関する希望等があり、法的な効力は発生しません。
したがって、付言事項の内容が、関係者を法的に拘束し、裁判等で認められ、強制的に実現されるという関係はありません。
3 付言事項の事実上の効果・影響
上記のとおり、付言事項自体に法的な拘束力はありませんが、遺言に記載された付言事項の意図を受け止めた相続人等が、遺言者の意思を尊重し、任意に遺言者の希望に沿った行為をした結果として、付言事項の内容が事実上実現されることはあります。
また、遺言に記載された付言事項が、遺言の効力及び内容の解釈等(*1)に影響を与える可能性もあります。
*1 遺言の解釈
「遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合に、そのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出し、その文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して、遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。」と示した最高裁判例があります(最判昭和58年3月18日)。
4 付言事項を考慮して遺言を無効とした裁判例
遺言の錯誤無効を認めた裁判例は少ないですが、さいたま地熊支判平成27年3月23日では、法的拘束力のない付言事項(相続財産のほぼ全ての包括遺贈を受ける者に対して、遺言者の子の生活費の負担を依頼する趣旨のもの)の存在が重視され、遺言者は、確実にその子に対して法的義務に基づき生活費等の支払いがされるものと誤信して、遺言をしていたと推認できるから、その遺言は錯誤(*2)により無効(*3)であるとされました。
*2 錯誤
錯誤とは、間違って真意と異なる意思を表示した場合(表示の錯誤)又は真意どおりに意思を表示しているがその真意が誤解に基づいていた場合(動機の錯誤)に、一定の要件に基づいてその意思表示を無効とする制度のことです。
*3 無効(民法改正)
上記裁判例で適用されていた改正前民法第95条では、錯誤の効果について(通常は誰でもその効力がないことを主張できる等の意味を有する)「無効」という文言が用いられていましたが、2020年4月1日に施行された改正民法では、「取消し」という文言に変更され、限られた取消権者(問題の意思表示をした者又はその承継人等)によって制限期間内に取り消された場合のみ、その意思表示がさかのぼって無効になると明確に規定されました(民法第120条、同第121条、同126条)。
また、改正民法では、錯誤の重要性及び(動機の錯誤の場合の)動機の表示という要件がそれぞれ明文化されています(同第95条)。
5 付言事項等に関する留意点
財産の承継等に関する法的効果を発生させる法定遺言事項だけでなく、付言事項を遺言に記載することにより、遺言者の意思や希望を相続人等の関係者に伝え、関係者に自身が望む行動を促すことは可能です。
しかし、法的拘束力がある事項とそうでない事項を区別して理解し、明確な区別をした遺言をしない場合、上記のように、結果的に真意と異なる遺言が作成され、その効力等について紛争が生じるリスクがあります。
したがって、遺言をする際には、自身が望む相続の在り方を明確にし、それを実現するため、法的効果を発生させる事項とそうではない事項を整理して、一義的に明らかな文言の遺言を作成することで、自身が望む相続を確実に実現し、事後の紛争を予防することが重要です。
※本記事の内容について細心の注意を払っていますが、その正確性及び完全性等の保証をするものではありません。本記事はその利用者に対し法的アドバイスを提供するものではありません。したがって、本記事の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、本ウェブサイトの提供者、本記事の著者及びその他の本記事の関係者は、かかる損害について一切の責任を負うものではありません。


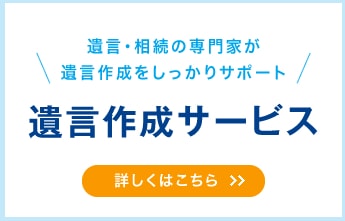
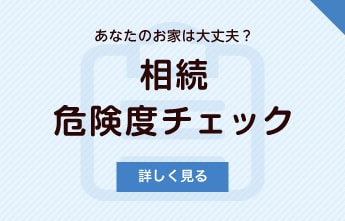
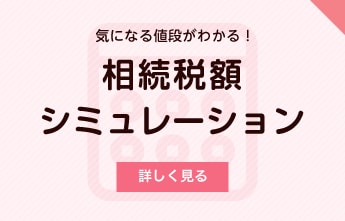

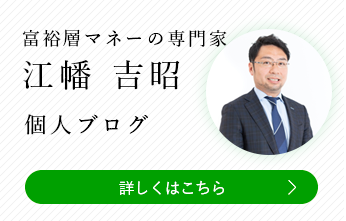
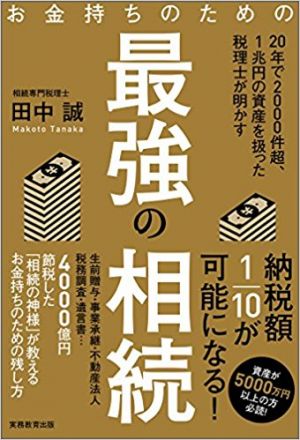
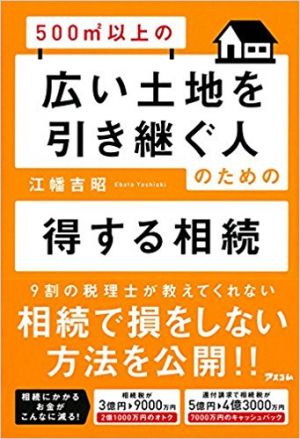
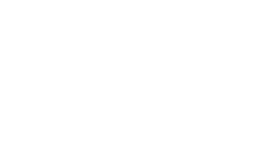 0120-131-554
0120-131-554