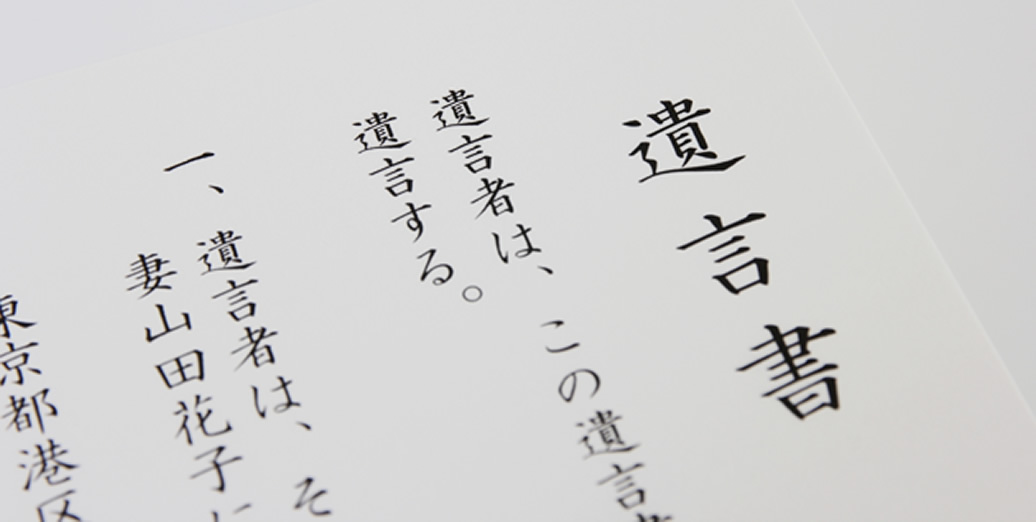
はじめに
前回まで、遺言執行についてご紹介しましたが、今回からは平成30年の民法改正により創設された「配偶者の居住の権利」についてご紹介します。
ご存知の方も多いかもしれませんが、改正民法では、相続・遺言に関して、いくつかの重要な法改正がなされました。その一つとして、被相続人の妻又は夫である配偶者(以下、「配偶者」といいます。)が被相続人の死亡後も生活を継続できるように、配偶者に生活の根幹となる居所の確保を可能とする配偶者の居住権に関する制度が創設されました。
配偶者の居住の権利には、大きく分けて「配偶者居住権」(民法第1028条~第1036条)と「配偶者短期居住権」(民法第1037条~第1041条)の二つがあります。権利の名前だけをみると「短期」が付くかどうかだけの違いであり、いずれも配偶者の居所を確保する権利という意味では共通しますが、成立要件や効果といった権利の中身や適用される場面などを比べると大きく異なります。
以下では、二つの権利のうち「配偶者居住権」について、創設された目的及びその成立要件について述べていきます。
配偶者居住権の創設された目的とは
昨今の高齢化社会の進展及び平均寿命の伸長に伴い、被相続人の配偶者が、被相続人の死亡後にも長期間にわたり生活を続けていくという場面が少なくありません。そして、被相続人の死亡による遺産分割の場面において、配偶者としては、それまで住んでいた住居での生活を確保しつつ、その後の生活資金として預貯金等の財産についても一定程度確保したいという希望を有する場合が多いと考えられます。
改正前の民法の下では、これを実現するために、①相続人間での遺産分割の中で配偶者が居住建物の所有権を取得するという方法や、②居住建物の所有権を取得した相続人等との間で賃貸借契約等を締結するという方法が考えられました。しかし、①の方法では居住建物の金額が高額となり、配偶者が居住建物以外の財産を十分に取得することができなくなる可能性があります。また、②の方法による場合、居住建物を取得した相続人等が賃貸借契約の締結に応じてもらうことが前提であるところ、必ずしも相続人等がこれに応じるとは限らないという可能性があります。
そこで、改正民法では、配偶者が居住建物を使用収益する権限「のみ」を認めた権利、つまり居住建物の売却等の処分を制限する権利である「配偶者居住権」を創設しました。このような配偶者居住権が認められることで、遺産分割の際に、配偶者が居住建物の所有権を取得する場合に比べて低い金額で居住権を確保しつつ、居住権以外の預貯金等の財産をも確保することが可能となります。
配偶者居住権の成立要件とは
配偶者居住権の成立要件は、①配偶者が被相続人の死亡時に被相続人の所有する建物に居住していたこと、②その建物について、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、や遺贈がなされることです。民法上の規定は以下のとおりです。
(配偶者居住権)
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
ここでの「配偶者」とは、被相続人の夫又は妻、つまり法律上被相続人と婚姻をしていた者をいいます。そのため、いわゆる「内縁の配偶者」は含まれません。
また、「居住建物」とは、被相続人の死亡の時点で被相続人が所有していた建物でなければなりません。そのため、被相続人が借りていた建物(借家)に配偶者が居住していた場合には、配偶者居住権は成立しません。そして、上記規定のただし書にもありますとおり、被相続人が配偶者以外の第三者と建物を共有していた場合には、配偶者居住権は成立しません。その裏返しとして、建物を被相続人と配偶者で共有していた場合には、配偶者居住権が成立する可能性があります。
「居住建物」に関して、配偶者が「居住していた」とは、どのような場合をいうかですが、これは配偶者が当該建物を生活の本拠としていたことを意味します。例えば、被相続人の死亡時に、配偶者が入院していたため、その時点では建物に住んでいなかったような場合でも、配偶者の家財道具がその建物に存在しており、退院後はそこに帰ることが予定されていた場合のように、配偶者の生活の本拠としての実態を失っていないと認められる場合には、配偶者は、なお、その建物に「居住していた」ということができます。このような生活の本拠は、通常1ヶ所であることが多いと思われますが、一定の期間ごとに生活の拠点を変えているような場合には、例外的に生活の本拠が複数あり、複数の建物について配偶者居住権が成立することもあり得ます。また、建物が店舗兼住宅であった場合でも、配偶者が当該建物の一部で生活をしていれば、建物に「居住していた」ということができます。
次回も、配偶者居住権についてご紹介します。
この記事へのお問い合わせ
弁護士法人マーキュリージェネラル
http://www.mercury-law.com/









 0120-131-554
0120-131-554