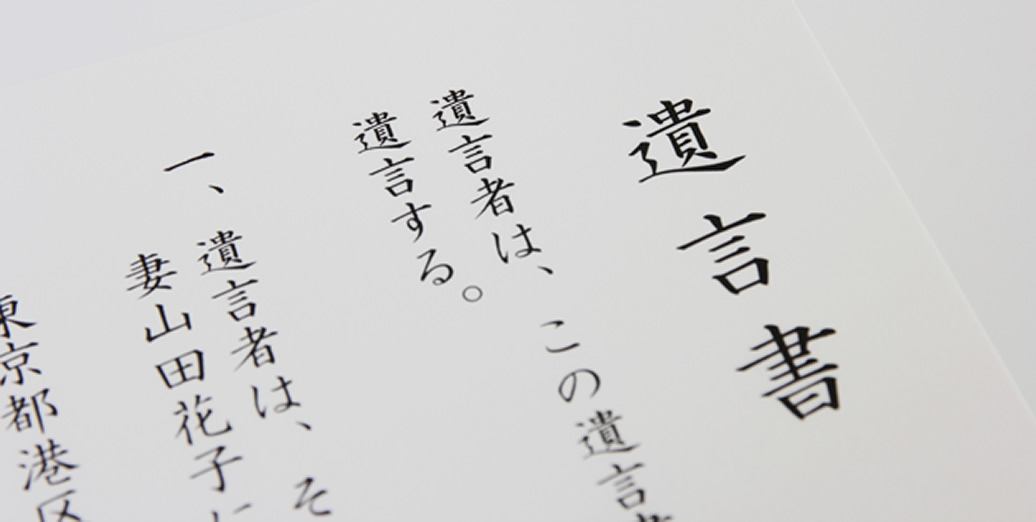
はじめに
前回(第18回)、「遺贈」、「相続分の指定」および「遺産分割方法の指定」についての類似点や相違点、効果の違いに関する具体例についてご紹介しましたが、今回は、“遺言の解釈”や“相続させる旨の遺言”についてご紹介いたします。
前回お話しましたとおり、遺言の内容が、相続分の指定なのか、遺産分割方法の指定なのか、それとも遺贈であるのか、が不明確な場合があります。遺産分割協議による当事者間の話し合いで、どのように解釈するかに疑義が生じなければ特段問題となりませんが、疑義が生じた場合、最終的に裁判所の判断で、遺言を解釈することになります。遺言を解釈することで、遺言の内容が確定し、その法的効果も確定することとなります。また、遺言の解釈に関連して、特定の財産を承継させる方法として「相続させる」旨の遺言というものがあります。かつて、この「相続させる」旨の遺言もどのように解釈されるかが問題となりましたが、現在は最高裁判例により解釈がある程度確立されています。
以下では遺言の解釈や、これに関連していわゆる「相続させる」旨の遺言について見てみましょう。
遺言の解釈とは
遺言は、当事者間の合意で成立する一般的な契約とは異なり、相手方の同意なく遺言者の意思のみで、財産を承継させるなどの効果を発生させます。つまり、遺言者が、遺言の作成時あるいは死亡時に、どのような意思を有していたかで、どのような効果が生じるか、ひいては遺言の解釈が決まります。したがって、遺言の解釈では、もっぱら遺言書に記載された遺言者の意思(遺言者が有していた真の意思ということで、以下「真意」といいます。)が探究され、かつ可能な限り有効に解釈すべきとされています。
真意の探究のためには、遺言書(解釈が問題となっている条項だけでなく、他の条項も含めた全体を指します)のほか、遺言書には記載されていない諸事情(遺言書作成当時の事情や遺言者が置かれていた状況など)を根拠として用います。遺言書には記載されていない事情を用いて真意の探究がなされた遺言書の内容が、一般的な言葉の意味と異なる場合でも、遺言者の意思が優先される結果、一般的な意味と異なる意味で解釈されることもあります。
また、複数の解釈の可能性があり、“遺言が有効となる解釈”と“無効となる解釈”の2通りが考えられる場合は、有効になる解釈が採用されるべきとされています。過去の事例[A1] でも、遺産を「公共に寄与する」旨の遺言について、一見すると受遺者が誰(どのような団体)か明らかとは言えない内容の遺言であり“無効”と解釈される余地もありえますが、裁判所は、上記遺言は、公共目的を達成できる団体等に遺贈する趣旨であり、かつ遺言執行者に受遺者として特定の者(団体)を選定することを委託する趣旨を含むとして“有効”と解釈したものが存在します。
[A1]最判平成5年1月19日民集47巻1号1頁
相続させる旨の遺言とは
遺言によって特定の人に、特定の財産を承継する方法としては、第16回でご紹介した「遺贈」の方法と「相続させる」という方法の2つがあります。いずれも、遺言書に特定の財産を特定の者に「遺贈する」または「相続させる」と記載することで効果が生じます。
いずれの方法を用いるかですが、まず、財産を承継する相手が法定相続人の場合、「遺贈する」ことも「相続させる」ことも両方可能です。しかし、相手が法定相続人ではない場合、「相続させる」と記載することは誤りです。なぜなら、法定相続人以外の人には、相続の効果が生じることはないからです。したがって、この場合は「遺贈する」と記載しなければなりません。もっとも、仮に、法定相続人以外の人に対して「相続させる」と記載していたとしても、前述の“遺言をできるだけ有効に解釈する”という考えのもと「遺贈する」と読み替えられる可能性がありますので、当該遺言が直ちに無効になるという訳ではありません。
相続させる旨の遺言の効果とは
特定の(あるいは全部の)遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、原則として、第17回でご紹介した「遺産分割方法の指定」をしたことになるとされます。つまり、遺産分割協議の時点で、すでに特定の相続人に当該財産が帰属(所有権が移転)したことになります。その結果、対象の財産が不動産の場合、当該相続人が、(他の相続人や遺言執行者の協力なくして)単独で“所有権を移転する”という内容の登記をすることができます。
ただし、遺産の全部ではなく一部を相続させるという内容の遺言の場合(例えば、「長男に遺産の3分の1を相続させる。」など)、どの財産を長男に帰属させるのかが不明ですので、これは「相続分の指定」と解釈され、遺産分割協議で財産の帰属を決める必要があります。
「相続させる」旨の遺言が、原則として遺産分割方法の指定と解されることから、「相続させる」旨の遺言と遺贈との効果の違いは、①債務の承継に関する取扱いと②代襲相続が生じた場合の取扱いです。
①債務の承継について
遺産分割方法の指定による財産の取得は、相続人の地位を有していることが前提になります。したがって、仮に遺産がプラスの財産をマイナスの財産が上回っている状態であることを理由に相続放棄をする場合、相続人の地位を失う結果、遺産分割方法の指定による財産取得の効果も失われます。他方で、遺贈の場合、相続人が相続放棄をするだけでは受遺者の地位を失う訳ではありませんので、相続放棄により債務やその他の財産を承継しないとする一方で、遺贈によって特定の財産のみ取得するということも可能です。
②代襲相続が生じた場合
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっている等の理由で相続人としての資格を有しない場合でもその相続人の子らが、代わりに相続人の資格を取得することを言います。遺贈の場合、被相続人よりも先に受遺者が死亡していた場合には、遺贈の効力は生じません(民法第九百九十四条第一項)。他方、相続させる旨の遺言の場合、遺言を解釈することで結論が異なることになります。遺言者が代襲相続させる意思を有していたとみるべき特別の事情があれば、代襲相続により本来の相続人の子らに対して、財産を承継させる効果が生じますが、特別な事情がなければ、遺言者の通常の意思としては、“その”相続人に対して財産を承継させる意思であると判断され、相続させる旨の遺言の効力は生じないこととなります。
次回は、遺言の執行についてご紹介します。

酒井 勝則
東京国際大学教養学部国際関係学科卒、
東京大学法科大学院修了、
ニューヨーク大学Master of Laws(LL.M.)Corporation Law Program修了








 0120-131-554
0120-131-554