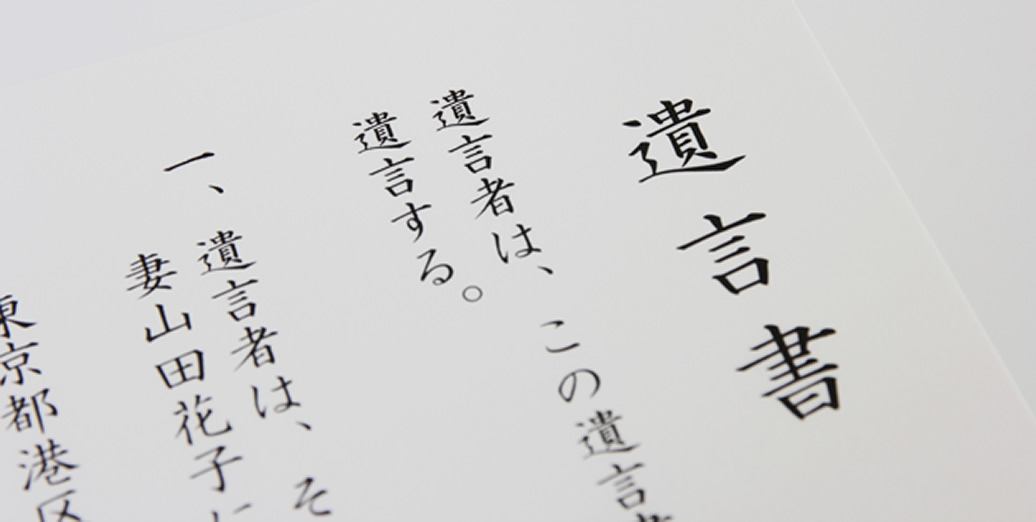
今回は、死後事務委任契約についてご説明します。
※ 本記事と関連する過去の記事
https://egonsouzoku.com/magazine/magazine-374/
https://egonsouzoku.com/magazine/magazine-1055/
https://egonsouzoku.com/magazine/magazine-1649/
https://egonsouzoku.com/magazine/magazine-1097/
1 死後事務委任契約
少子高齢化が進む中で、家族関係が希薄になり、ご自身の死後に、葬儀、永代供養の実施と費用の支払い等を信頼できる人に依頼したいというニーズが高まっています。
このニーズに対応するため、葬儀の実施等の死後の事務を第三者に委任する合意がされることがあります。
このような合意は、一般的に死後事務委任契約と呼ばれています。
なお、委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することで成立する契約とされています(民法第643条)。死後事務委任契約は、法律行為でない事務を委託するものであり、委任契約には該当しませんが、このような場合も準委任契約として委任契約に関する民法の規定が準用されることになります(民法第656条)。
2 死後事務委任契約の特徴
身近な親族がいる場合、その親族が相続人として、相続手続の一環として死後の事務を行うことが多いです。他方で、身近な親族がいない場合、すなわち相続人がいない場合や、相続人がいるとしても疎遠な親族であり、死後の事務まで任せることができない場合は、親族以外の信頼できる第三者に死後の事務を任せる方法として、死後事務委任契約は有用です。
なお、後述「3 死後事務委任契約の有効性」で説明しますように、一定の条件を満たせば、委任者の生前に締結された死後事務委任契約は委任者の死亡後も有効に存続し、かつ、相続人による解除を防止することができます。
もっとも、ご自身が存命中でも、認知症等により判断能力が低下すると、契約を有効に締結できなくなる可能性があります。そのような状態になる前に、死後の事務の内容とそれを任せる人を準備し、死後事務委任契約を締結しておくべきです。
ただし、遺産の相続や贈与は、死後事務委任契約ではなく、遺言や死因贈与契約等の別の方式で行うべきとされている点には注意が必要です。
3 死後事務委任契約の有効性
委任者の死後における契約の存続(有効性)及び解除の制限について議論がありますが、原則として、委任者の死後においても死後事務委任契約は有効なものとして存続し、解除の制限も有効であると解されています。
(1) 委任者死亡後の契約の有効性
委任契約においては、「委任者又は受任者の死亡」(民法第653条1号)が終了事由として規定されています。
前述のとおり、死後事務委任契約も準委任契約として委任契約の規定が準用されますので、委任者の死後も、死後事務委任契約が有効であるか否かが問題になります。
この点、民法第653条は強行規定ではなく、これと異なる内容の特約が許されると解されています。
また判例でも、自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約は、委任者の死亡によってもその契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨であり、その合意は有効であるとされています(最判平成4年9月22日金法1358号55頁)。
したがって、委任者の死後も終了しない旨の特約がある死後事務委任契約は、委任者の死後も有効に存続すると解されています。
(2) 委任者死亡後の相続人による契約解除を制限する特約の有効性
委任契約において、各当事者はいつでもその解除をすることができますので(民法第651条1項)、委任者の死後にその相続人は死後事務委任契約を解除することができることになります。自己の死後の事務を委託する委任者としては、このような解除を制限する必要がありますので、その相続人が契約を解除できないという特約が、有効であるかが問題となります。
この点、相続人が契約を解除できないとすることが相続人の意思を制限し、相続人を不当に拘束する場合でない限り、解除権を制限する合意は有効で、委任者の相続人を拘束すると解されています。
また、「委任者の死亡後における事務処理を依頼する旨の委任契約においては、委任者は、自己の死亡後に契約に従って事務が履行されることを想定して契約を締結しているのであるから、その契約内容が不明確又は実現困難であったり、委任者の地位を承継したものにとって履行負担が過重であるなど契約を履行させることが不合理と認められる特段の事情がない限り、委任者の地位の承継者が委任契約を解除して終了させることを許さない合意を包含する趣旨と解することが相当である」とした裁判例(東京高判平成21年12月21日)があります。
したがって、原則として、解除権を制限する合意を含む死後事務委任契約は、相続人によって解除できないと解されています。
4 財産承継の手段との組み合わせ
死後事務委任契約に遺産の相続や贈与等の財産承継を含めることは、それぞれの法的性質が異なるため難しいですが、財産承継等を行わせる方法としては、以下が考えられます。死後事務委任契約とこれらの財産承継の方法を組み合わせることで、ご自身の意思に基づいた死後事務と財産承継を実施することができます。
(1) 死因贈与契約
死因贈与契約とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる、贈与者と受贈者との間の贈与契約です(民法第554条)
(2) 遺言
遺言とは、自己の死亡時に存在する財産の処分等に関する意思表示のことです(民法第964条等)。当事者間の合意で成立する死因贈与契約とは異なり、遺言者の一方的な意思表示で行うことができます。
また、遺言で遺言執行者を指定する等の方法により、遺言執行者に、預貯金の払い戻し及び不動産の登記申請手続き等、遺言の内容の実現に必要な事務を担ってもらうことができます。
(3) その他
①生前の財産管理にも利用できる特徴をもつ遺言代用信託、又は②遺言者の死亡後に相続人が財産を管理する能力が無い場合等に利用される遺言信託を利用して、受託者による財産管理を通じて、(残された高齢家族の療養看護のための財産管理を含めた)財産の管理・利用をすることもできます。
5 まとめ
死後に委任する事務の内容、委任者の死後も契約が有効に存続する旨及び委任者の死後の相続人の契約解除権を制限する旨を明記した死後事務委任契約書を作成することで、後の紛争を予防することができます。
少子高齢化社会においては、葬儀の実施等の死後の事務、財産の管理・承継及び残された家族の扶養・療養看護等について、生前に準備しておく必要性が高まっています。
死後事務委任契約や遺言等のそれぞれの特徴を理解して、ご自身の死後であってもその意思を実現するために、適切な準備をされることをお勧めします。
※本記事の内容について細心の注意を払っていますが、その正確性及び完全性等の保証をするものではありません。本記事はその利用者に対し法的アドバイスを提供するものではありません。したがって、本記事の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、本ウェブサイトの提供者、本記事の著者及びその他の本記事の関係者は、かかる損害について一切の責任を負うものではありません。


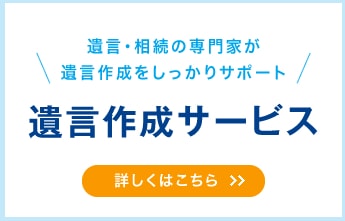
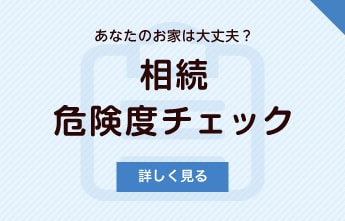
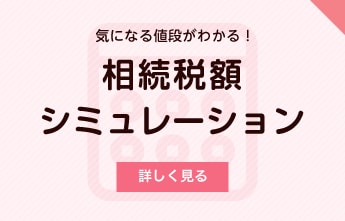

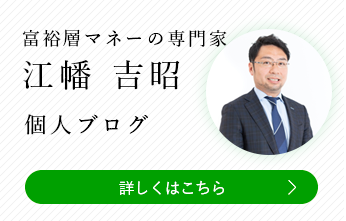
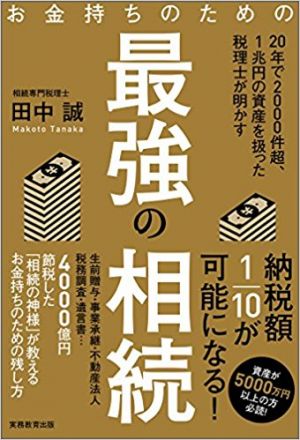
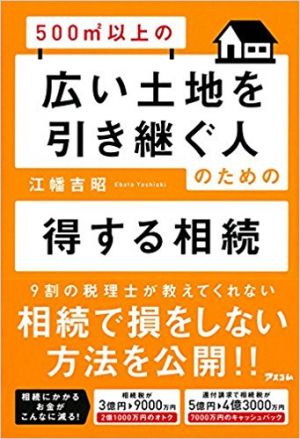
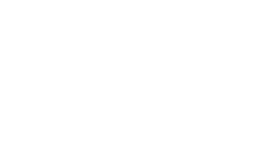 0120-131-554
0120-131-554