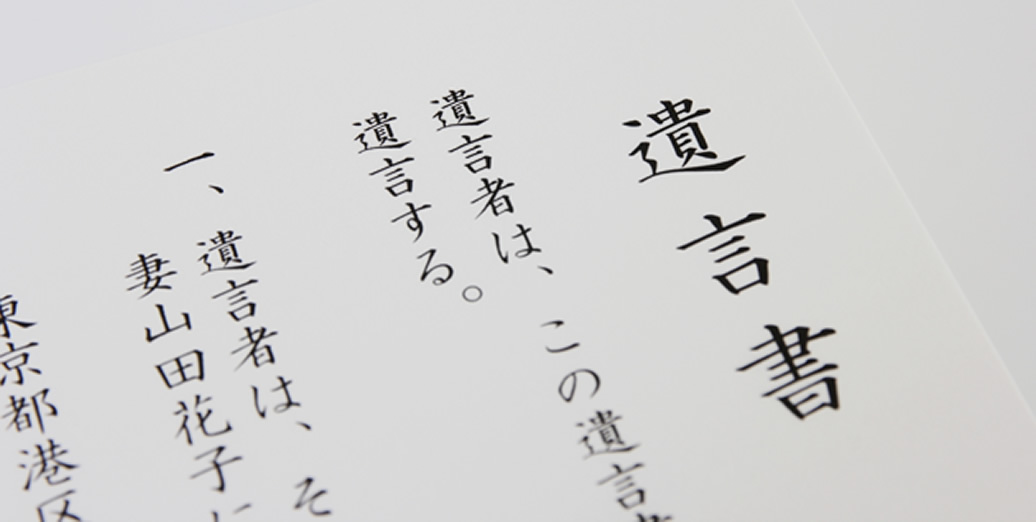
遺言能力とは? 遺言能力がない人が作成した遺言は、どのように取り扱われるの?
前回は、遺言を作成する方式について、ご紹介をしましたが、今回は、遺言能力について、解説を致します。
遺言能力とは、本人が遺言をするに当たり、その遺言の内容、及び、その遺言の結果生じる法律効果を理解し判断できる能力のことです。遺言能力がない者が作成した遺言は、たとえ形式的な遺言の作成要件を満たしていたとしても、遺言は無効となってしまいます。
遺言作成者が死亡後、この遺言能力が欠けているという理由が主張されて、遺言書の効力が争われる場合が少なくありません。実際に、特に高齢者が作成した遺言について、遺言能力が否定されて、せっかく手間と時間をかけて作成した遺言が、無効と判断されたケースも少なからず存在しております。したがって、遺言能力が問題となる場面を理解して、必要な対策をしておくことが重要です。
遺言能力の有無についての民法上のルールは、どのような内容なの?
有効に取引を行うことができるいわゆる行為能力については、民法は、20歳以上の者に原則として行為能力を認めていますが、有効に遺言を行うことができる遺言能力についての原則は、以下のとおり定められています。
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第九百六十二条 第五条(未成年者の法律行為)、第九条(成年被後見人の法律行為)、第十三条(保佐人の同意を要する行為等)及び第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)の規定は、遺言については、適用しない。
つまり、遺言能力は原則として15歳以上の者に認められ、取引をする能力が制限されている19歳以下の未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人であっても、15歳以上であれば遺言能力が認められる可能性があることになります。
また、成年被後見人については、以下の規定が存在しています。
(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
したがって、成年被後見人が遺言をする場合には、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師2人以上が立ち会い、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態に無かった旨を遺言書に付記して署名・押印する等の手続が必要になります。
遺言能力の有無は、どのように判断されるの?
民法に明文で定められている基本的なルールは上記のとおりですが、15才以上であれば、誰でも遺言能力が認められる訳ではなく、以下のとおり、遺言をする時点において、その遺言の内容、及び、その遺言の結果生じる法律効果を理解し判断できる遺言能力を有していることが必要です。
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
遺言能力への配慮が特に必要になるのは、高齢者が遺言書を作成する場合です。高齢者は、加齢とともに判断能力が低下しますので、死亡後に遺言能力が無かったとして、遺言書の効力が裁判上争われることが少なくありません。
遺言能力が争点となった裁判例においては、遺言能力の有無は、主として以下の点が考慮されています。
①遺言作成の経緯・動機
②遺言の内容を理解して作成しているか(内容の複雑さ)
③遺言作成時の状況(他者からの影響の有無など)
④認知症の影響などの遺言者の精神上の障害の有無、内容、程度
⑤認知症の病状の変化
遺言能力を有していたことは、どのように証拠にすればよいの?
遺言者が高齢である場合や、認知症である場合など、その遺言能力が問題となる可能性があると思われる場合には、遺言作成時に、遺言者の病気に関する事項や、遺言作成時の会話など、その判断能力を基礎づける事実について、可能な限り詳細な記録を残しておく必要があります。
望ましい方法としては、(1)医師に認知症の疑いがないかどうかについてテストを行ってもらい、診断書などの形式で記録に残す、(2)遺言者が遺言を作成する様子をビデオ撮影するなどの方法が挙げられます。

酒井 勝則
東京国際大学教養学部国際関係学科卒、
東京大学法科大学院修了、
ニューヨーク大学Master of Laws(LL.M.)Corporation Law Program修了








 0120-131-554
0120-131-554