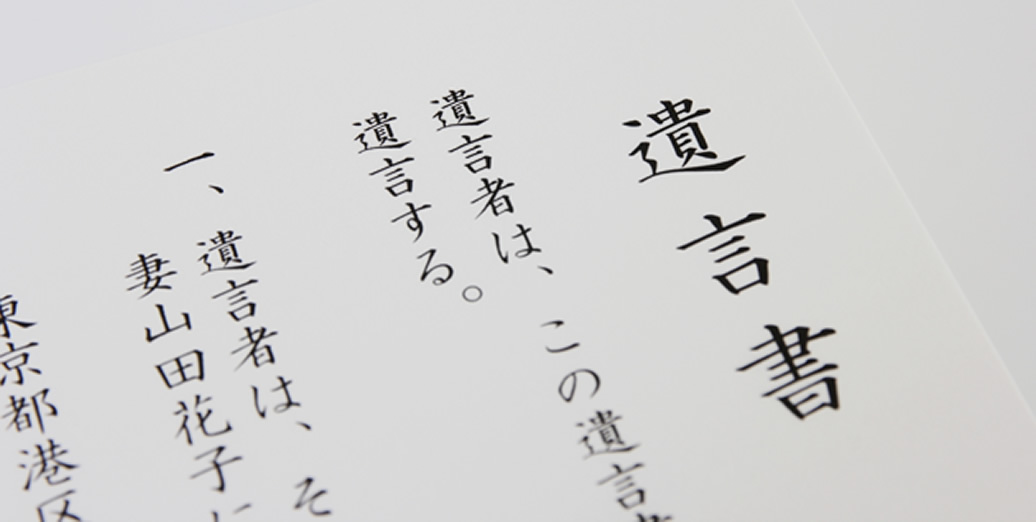
はじめに
前回、被相続人(遺言者)の妻または夫である配偶者(以下、「配偶者」といいます。)の居住の権利である「配偶者居住権」の成立要件のうち、遺産分割による当該権利の取得についてご紹介しました。
配偶者居住権の成立要件は、①配偶者が被相続人の死亡時に被相続人の所有する建物に居住していたこと、②その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割や遺贈がなされることの二つです。
ところが、実際の事例では、建物の状況や権利関係により、上記要件を充足するかどうかの判断に窮する場面がありえます。
そこで、以下では、配偶者居住権の成立要件の充足判断に窮する可能性のある事例をピックアップし、要件充足の可否について述べていきます。
居住建物が店舗兼住宅であった場合
配偶者が、被相続人の死亡時に居住していた建物(以下、「居住建物」といいます。)が、一般的な一戸建てやマンションではなく、店舗兼住宅であった場合に、配偶者居住権の成立要件①を充足するかどうかが問題となります。
この点、上記成立要件①によると、「建物に居住していたこと」が必要とされていますが、建物の「全体」に居住していたことまで要件として定められている訳ではありません。
したがって、店舗兼住宅の場合であっても、配偶者が、建物の一部で居住していたと判断される場合、「建物に居住していたこと」という要件を充足することになります。
もっとも、上記の結論からすると、配偶者が、被相続人の死亡時に居住建物の一部に居住していた場合であっても、配偶者居住権の効力は建物の全部に及ぶことになるため、配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の全部について、使用したり営業活動により収益をあげたりすることができることになります。これは、建物の一部について配偶者居住権が成立することを認めると、配偶者は居住建物全体についての配偶者居住権を取得するよりも低い評価額で配偶者居住権を取得することができることになり、建物の明渡し等の強制執行を妨害する目的で、当該権利を利用される可能性があること、建物の一部について不動産登記を備えることが技術的に困難であること等を考慮したものになります。
したがって、店舗兼住宅であっても、配偶者に居住実態が認められれば、配偶者居住権が居住建物全体に成立する可能性が高いでしょう。
居住建物の一部が賃貸に出されている場合
居住建物に、配偶者だけでなく、第三者が被相続人から賃借して居住しているという場合、配偶者居住権の成立要件①を充足するかどうかが問題となります。
この点、被相続人の死亡時に、第三者が居住建物に住んでいたとしても、配偶者が当該居住建物にて居住していれば、居住建物の所有者との関係では、「建物に居住していたこと」という要件を充足することになります。この場合、配偶者は、配偶者居住権に基づいて、前記店舗兼住宅の場合と同様に居住建物全体を使用し、収益することができます。そうすると、配偶者としては、居住建物全体を使用するために、当該第三者である賃借人に建物から退去してほしいと考える方もいるかもしれません。しかし、賃借人としては、自身で関与できない被相続人の死亡=居住建物の相続及び配偶者居住権の成立により配偶者から建物の退去を求められたのではたまりません。そこで、賃借人は、配偶者に配偶者居住権が成立するとしても、その前から居住建物を賃借して利用している場合、依然として居住建物を賃借し続けることができます。
したがって、配偶者は、居住建物に賃借人がいるとしても、配偶者居住権の成立が認められますが、当該賃借人に建物からの退去まで求めることはできません。
被相続人が第三者または配偶者と居住建物を共有していた場合
被相続人が、建物全部を所有しているのではなく共有持分を持っているだけの場合、原則として、配偶者による配偶者居住権の成立は認められません。民法上の規定は以下のとおりです。
(配偶者居住権)
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
配偶者居住権は、配偶者が建物使用の対価を支払うことなく当該建物を利用する権利を取得することができるところにその存在意義がありますが、被相続人が建物を配偶者以外の第三者と共有していた場合にまで配偶者居住権の成立を認めると、被相続人の死亡により当該第三者の共有持分の価値が不当に侵害(減額)されることになることを考慮して、上記結論が採用されるに至りました。
もっとも、例外的に、居住建物が被相続人と配偶者のみで共有となっていた場合には、配偶者居住権の成立を認めることとされています。これは夫婦が居住する建物については夫婦の共有となっている場合も相当程度存在すると考えられることから、配偶者居住権を成立させる必要性があることと、第三者との共有の場合で当該第三者が被るような共有持分の価値の不当な侵害(減額)を受けることがないということが理由とされます。
したがいまして、居住建物が被相続人と配偶者のみで共有となっている場合には、配偶者居住権の成立の余地がある一方で、被相続人と配偶者以外の第三者で共有となっている場合には、配偶者居住権は成立しないこととなります。
配偶者居住権の成立要件の充足判断に窮する可能性のある事例に関する説明は以上になります。次回も、配偶者居住権についてご紹介します。
この記事へのお問い合わせ
弁護士法人マーキュリージェネラル
http://www.mercury-law.com/









 0120-131-554
0120-131-554