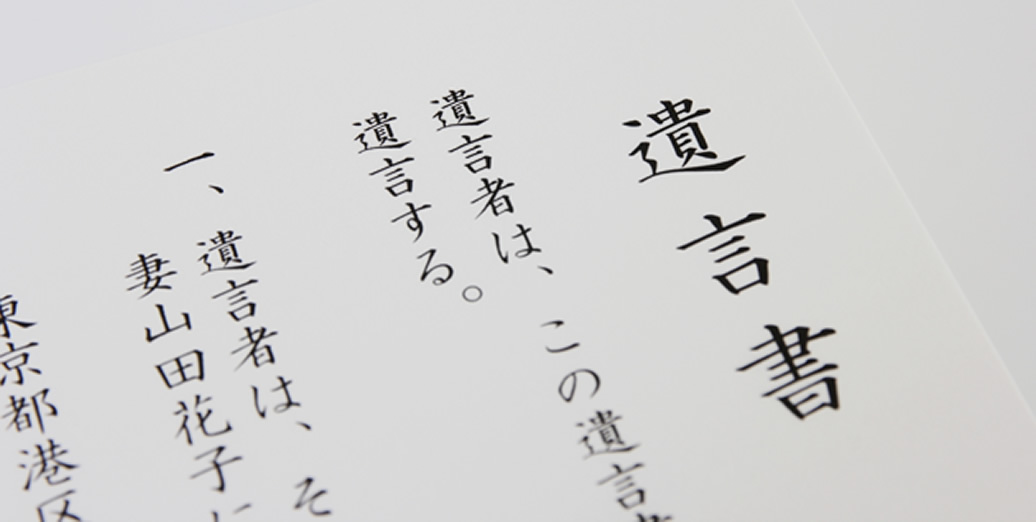
はじめに
前回、遺言執行者がある場合の相続人による処分行為等が制限される場合や制限される処分行為等の内容に関してご紹介しましたが、今回は、遺言執行者がある場合に遺言執行を妨げるべき行為が行われた場合の効果等についてご紹介します。
従前ご説明したとおり、遺言執行者は、遺言の内容を実現し、遺言に基づく権利の実現とそれに関連して必要となる事務を行う者であるところ、遺言の内容をスムーズに実現するために遺言執行者を指定・選任しておくことが有益です。
そして、遺言執行者を指定・選任しておくことのメリットの一つとして、相続人が相続財産を他の相続人に無断で処分してしまうことを防ぐということが挙げられます。もっとも、相続人が無断で相続財産を処分するという場合、“何も事情を知らない”当該相続財産の譲受人が登場し、この者の保護をいかにして図るかを検討する必要が出てきます。
以下では、相続人による遺言執行を妨げるべき行為が行われた場合の効果及び当該行為により相続財産を譲り受けた譲受人の保護について具体例を交えながら述べていきます。
相続人による遺言執行を妨げるべき行為が行われた場合の効果とは
前回、「遺言執行を妨げるべき行為」として、対象となる相続財産を売却することに限らず、当該相続財産の現状を変更する行為等も含むとご説明しましたが、遺言執行者がある場合にこのような行為が行われたときの効果に関する民法上の規定は以下のとおりです。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
平成30年の民法改正前の規定では、上記規定の第2項はなく、第1項のみでした。第1項の記載は、あくまでも遺言執行を妨げるべき行為を禁止するというものですが、この規定の解釈として、当該行為が行われた場合の効果については、第2項の記載にあるとおり、「無効」とされていました。
民法上の「無効」とは、事実として行われた意思表示や法律行為を法的には“そもそもなかったものとして扱う”ことをいいます。そして、この「無効」には、全ての人が無効を主張できる「絶対的無効」というものと、一定の限られた人しか無効を主張することができない「相対的無効」の2種類があります。
この点、上記遺言執行を妨げるべき行為が行われた場合の「無効」がどちらを意味するのかについて、最高裁判所(及びその前身である大審院)は、一貫して、「絶対的無効」を意味するという見解を示していました(大判昭和5年6月16日民集9巻550頁、最判昭和62年4月23日民集41巻3号474頁)。
この「絶対的無効」の意味について、具体例をみてみましょう。
遺言者(被相続人)Aには唯一の相続人としてBがいましたが、Aは、Aの友人Cに土地を遺贈する旨の遺言を作成し、かつ遺言執行者を指定していました。この場合、相続人Bとしては、Cに遺贈するとされた土地について、何も処分する権限をもたないことになります。仮に、Bが、当該遺言に反して、無関係なDに、土地を売却し、その旨の不動産登記を行ったとしても、Cは、BD間の土地の売買契約が無効であること及び土地の所有権がDではなくCにあることを主張することができます。
絶対的無効ということの意味は上記のとおりですが、上記の結論は、Cにとって喜ばしいものである一方で、何も事情を知らずに土地を買い受けていたDにとっては、代金をBに支払ったにもかかわらず土地の所有権を取得することができないという酷な結論になってしまいます。また、Dとしては、Aの相続にあたり遺言があるかどうか、遺言執行者が指定されているかどうかなど通常知り得ないこともあいまって、より一層酷な結論となってしまいます。そこで、このようなDを保護するため、平成30年の民法改正により、遺言執行を妨げるべき行為をした場合の効果と例外的に「善意の第三者」を保護するという民法第1013条第2項が創設されました。
民法第1013条第2項の創設の経緯とは
平成30年の民法改正前においても、上記のようなDをどのような要件のもと保護すべきか、すなわち、BD間の売買契約が無効であるとしつつ、Dに土地の所有権を帰属させるべきかどうか、帰属させるべき場合があるとしてどのような要件が必要であるかが、盛んに議論されていました。
しかし、過去の裁判例では、上記のとおり遺言執行を妨げるべき行為をした場合の効果として「絶対的無効」であることを理由として、Dの所有権を認めないと判断されました(名古屋高判昭和58年11月21日判時1107号80頁)。
このような状況の中、平成30年の民法改正の際、やはり遺言執行者の有無についての事情を知らないDは保護すべきという方向で議論がなされました。その方策として、旧法の民法第1013条自体を削除し、CとDのどちらに所有権を帰属させるかを不動産登記の先後で決めるという案も提出されましたが、最終的にDが「善意の第三者」に当たる場合に保護するという結論に至りました。
「善意の第三者」に当たる場合とは
ここでいう「善意」とは、日常的に用いられる親切心や好意という意味ではなく、“ある事実を知らないこと”を意味します。つまり、民法第1013条第2項の善意とは、Bが土地について処分権限を有しないこと、Aが遺言を作成し、遺言執行者を指定していることについて知らないことを意味します。
この点、平成30年の民法改正における議論の中では、単に上記事情を知らないDではなく、事情を知らないことについて過失のないDに限定して保護すべきではないかということも検討されました。つまり、Dとしては、売買契約時にBに処分権限がないことを知らなかったとしても、調査によって調べることができた場合には、「善意の第三者」に含まれないこととする、という方策も検討されました。しかしながら、Aが遺言執行者を指定しているかどうかを公に明らかにするような手段がない以上、Dに遺言執行者の有無について調査義務を課すことは相当でないという意見が採用され、上記のとおり単に「善意」であれば足りるとされました。
遺言執行者がある場合に遺言執行を妨げるべき行為が行われた場合の効果等に関する説明は以上になります。平成30年民法改正により、これまでの裁判例とは異なる扱いをすることが明確になりましたので、相続実務への影響が相当程度大きくなるものと予想されます。次回は、遺言執行を終了する場合の手続き等についてご紹介します。
この記事へのお問い合わせ
弁護士法人マーキュリージェネラル
http://www.mercury-law.com/









 0120-131-554
0120-131-554