
遺産分割協議の有効性が問題となる場合について
はじめに
前回に続いて、遺産分割における諸問題についてのまとめ解説の第6回目となります。
今回は、遺産分割協議の有効性が問題となる場合について解説いたします。
意思能力の欠如
遺産分割協議は、共同相続人全員の合意に基づいて成立する契約行為であるため、その合意の前提として、遺産分割協議の意思表示の際に、共同相続人全員に意思能力があること、すなわち当該遺産分割協議の内容を理解し、判断する能力があることが必要となります。
よって、遺産分割協議に参加した共同相続人に一人でも意思能力を欠く者が含まれていた場合、その遺産分割協議は無効となります(民法第3条の2)。
(1) 意思能力の有無が問題となる場面
共同相続人の中に認知症を患っている相続人がいる場合、当該相続人の意思能力の有無が問題となります。もっとも、認知症を患っている相続人のすべてが意思能力を欠くというわけではなく、医師の診断によって「遺産分割協議に必要な意思能力がある」と認められれば、本人の意思で協議に参加できる場合もあります。
(2) 意思能力を欠く相続人がいる場合に遺産分割協議を有効に進めるための方法
認知症の進行等により、意思能力を欠く相続人がいる場合に、遺産分割協議を有効に進めるためには、成年後見制度を利用し、成年後見人を選任することが最も一般的な解決策です。
① 成年後見制度
成年後見人は、判断能力が低下した本人に代わって、財産管理や法律行為を行います。遺産分割協議においては、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加し、合意を形成することになります。
なお、成年後見人は本人の代理人ですので、遺産分割協議においても、本人の利益が損なわれないように遺産分割協議を行う必要があります。よって、本人の法定相続分を下回るような内容で合意することは、原則として認められないとされています。
② 特別代理人
成年後見人が選任されている場合であっても、成年後見人と本人(意思能力を欠く相続人)が共に相続人である場合は、遺産分割協議において成年後見人と本人の利益が相反する関係にあるため、本人のために特別代理人を選任する必要があります。
但し、本人に成年後見人のみならず成年後見監督人も選任されている場合は、成年後見監督人が本人を代理して遺産分割協議に参加することになるため、特別代理人を選任する必要はありません。
意思表示の瑕疵
前述のとおり遺産分割協議は、共同相続人全員の合意に基づいて成立する契約行為であるため、民法の意思表示に関する規定が適用されます。そのため、以下のような意思表示の瑕疵があった場合、その協議の有効性が問題になります。具体的には以下の場合です。
(1) 錯誤(民法第95条)
遺産分割協議の意思表示について錯誤を認めた判例・裁判例には、以下のものがあります。
① 遺産に含まれる土地について、相続人A、B及びCに相続させる旨の分割方法を定めた遺言の存在を知らずに、相続人Dが当該土地全部を相続するという遺言の趣旨とは異なる遺産分割協議がなされた場合、相続人Aは、遺言を知っていればそのような遺産分割協議の意思表示をしなかった蓋然性が高いとして、相続人Aに錯誤が認められた事例(最判平成5年12月16日)。
② 他の共同相続人が、本当は預金が2,400万円以上あったにもかかわらず、1,900万円しかないという虚偽の説明をしたことにより、遺産である預金について実際よりも低額と誤信して遺産分割協議の意思表示をした場合に錯誤が認められた事例(広島高裁松江支部平成2年9月25日)。
なお、遺産分割協議の意思表示に錯誤があった場合、当該遺産分割は無効とされていましたが、令和2年4月1日に施行された民法改正により、錯誤による意思表示は無効ではなく取り消し得るものとなりました。したがいまして、錯誤により遺産分割協議が令和2年3月31日までに行われたものであれば、当該遺産分割は無効となり、同年4月1日以降に行われたものであれば、取り消し得るものとなります。
(2) 詐欺・強迫(民法96条)
相続人による遺産分割協議の意思表示が、他の相続人の故意による欺罔行為によるものである場合、当該相続人は詐欺を理由に遺産分割協議を取り消すことができます(民法第96条)。
また、他の相続人から違法な強迫を受け、それによる恐怖心から遺産分割協議の意思表示を行った場合は、当該相続人は強迫を理由に遺産分割協議を取り消すことができます(民法96条)。そして、詐欺又は強迫を理由とした取消権が行使された場合、遺産分割協議は遡って無効となります(民法121条)。
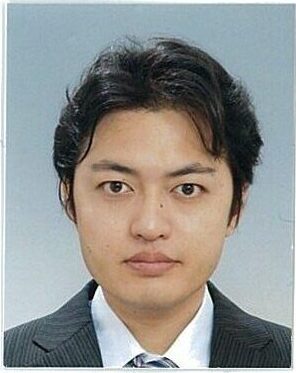

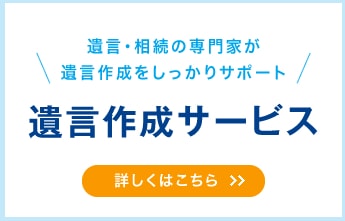
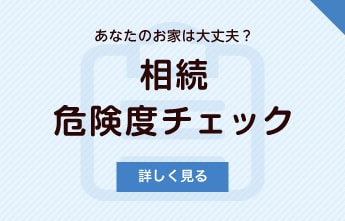
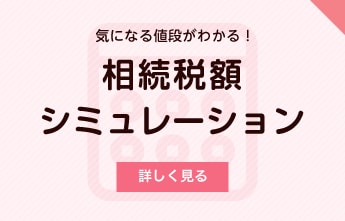

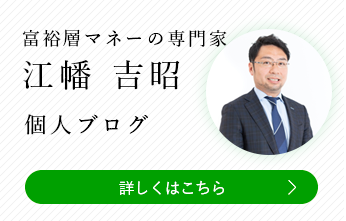
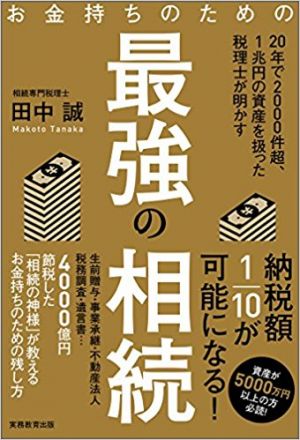
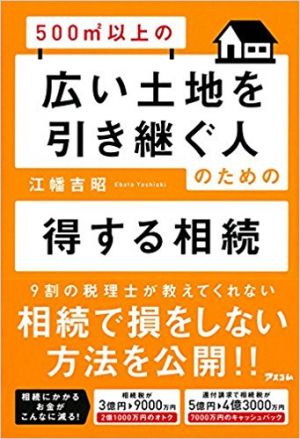
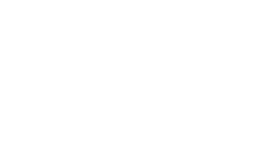 0120-131-554
0120-131-554