
今回は、生命保険金の受取人の変更等についてご説明します。
※ 本記事と関連する過去の記事
https://egonsouzoku.com/magazine/magazine-148/
https://egonsouzoku.com/magazine/magazine-239/
1 相続の対象の範囲(生命保険金の位置づけ)
民法では「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定されており(民法第896条)、原則として、被相続人が有していた全ての権利義務が承継されます。
しかし、生命保険金の受取人が特定の相続人とされている場合、生命保険金は相続財産には含まれず、相続の対象とはなりません。これは、生命保険金の請求権は、保険契約の効果として、その受取人の固有財産に属すると考えられているためです。
したがって、生命保険金の帰属については、相続による承継ではなく、その保険契約に基づいて考える必要があります。
2 保険金受取人の変更
一般的には、生命保険契約の締結時に、保険金受取人が指定されます。しかし、生命保険契約は、長期の契約であり、その期間中に多くの事情が変わります。その事情に応じて、保険契約者が保険金受取人を変更することを認める必要があります。
そこで、保険契約者は、保険事故(生命保険の場合は被保険者が死亡すること)が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができます(保険法第43条第1項)。
この保険金受取人の変更の意思表示は、保険者(保険会社)に対する意思表示によってしなければなりません(保険法第43条第2項)。
なお、保険約款等で、生命保険金受取人の範囲が、配偶者及び一定の範囲の血族に限定されている場合が多いため、生命保険金の受取人の変更をする場合には、事前に保険会社に問い合わせて確認をしておく必要があります。
3 遺言による保険金受取人の変更
上記のとおり、保険金受取人が指定されている生命保険契約は、相続の対象にはなりません。
他方で、保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができます(保険法第44条第1項)。
ただし、遺言による保険金受取人の変更のためには、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者(保険会社)に対抗することができません(保険法第44条第2項)。
その通知が速やかに行われない場合、保険会社が変更前の生命保険金受取人に対して保険金を支払ってしまい、紛争が生じるリスクがあります。
そこで、遺言で弁護士等の専門家を遺言執行者として指定し、遺言執行者によりこの通知がされる旨を定めておくことで、遺言による生命保険金受取人の変更をより安全にすることが可能です。
4 遺言作成時の注意点
上記のとおり、生命保険金の受取人を遺言によって変更することは可能ですが、変更の通知が速やかにされずに紛争が生じるリスクもあります。
生命保険金受取人の変更をしようとする場合、生命保険金が相続財産に含まれない可能性があること、生命保険金受取人の範囲が制限されている可能性があること、遺言による変更の場合は速やかな通知が必要であること等を理解し、適切な方法で行うことが重要です。
※本記事の内容について細心の注意を払っていますが、その正確性及び完全性等の保証をするものではありません。本記事はその利用者に対し法的アドバイスを提供するものではありません。したがって、本記事の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、本ウェブサイトの提供者、本記事の著者及びその他の本記事の関係者は、かかる損害について一切の責任を負うものではありません。


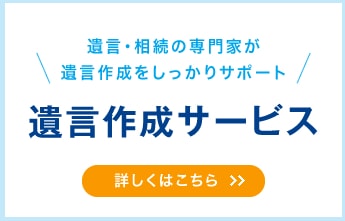
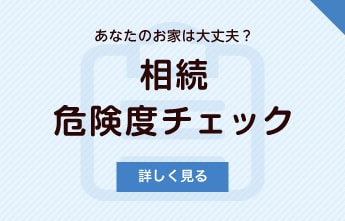
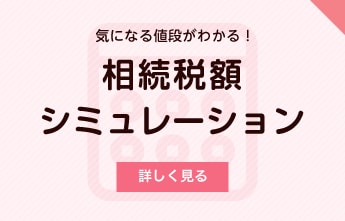

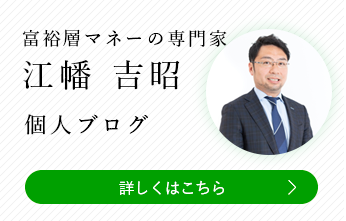
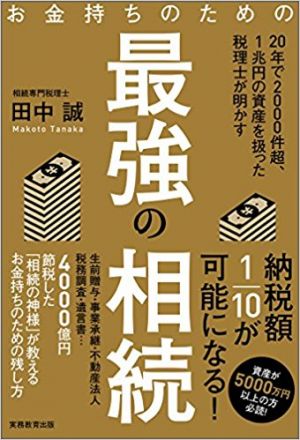
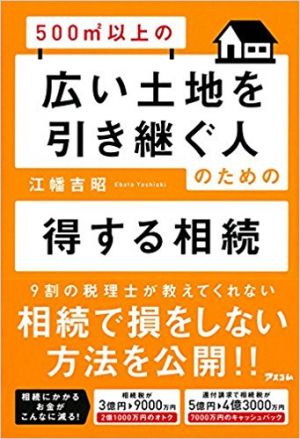
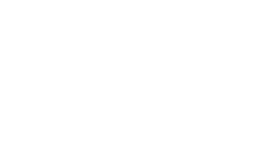 0120-131-554
0120-131-554