
遺産分割の手続及び方法の概要
はじめに
前回に続いて、遺産分割における諸問題についてのまとめ解説の第5回目となります。
今回は、遺産分割の手続及び方法の概要についてご説明いたします。
遺産分割の手続
遺産分割の手続には、以下の3つの手続があります。
①協議分割
協議分割とは、相続人全員の話し合いにより、被相続人の遺産を分割する手続を意味します(民法907条1項)
②調停分割
調停分割とは、上記①の協議ができない場合又は協議が調わない場合に、家庭裁判所の調停委員会が仲介に入り、話し合いで解決を目指す手続を意味します(民法907条2項)。相続人全員が合意できれば調停が成立し、遺産分割が進められます。
③審判分割
審判分割とは、上記①の協議ができない場合又は協議が調わない場合で、上記②の調停でも解決に至らなかった場合に、家庭裁判所が遺産の分割方法を決定する手続を意味します(民法907条2項)。審判分割においては、裁判官が当事者の主張や提出された資料に基づいて、法律に従って遺産分割の方法を決定します。
遺産分割の方法
遺産分割の方法には、以下の4つの方法があります。
①現物分割
現物分割とは、個々の相続財産の形状や性質を変更することなく、そのままの形で各相続人に分配する方法を意味します。例えば、土地と建物は妻に、現金は子にというように、各相続人が特定の財産をそのまま直接受け継ぐ場合が現物分割となります。
②代償分割
代償分割とは、一部の相続人に法定相続分を超える額の相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した相続人が他の相続人に対して債務を負担する方法を意味します。例えば、相続財産が1億円の土地のみで、相続人が妻と子の場合、妻に当該土地を取得させ、その代償として妻が子に対して、子の相続分に相当する5,000万円を支払うという分割方法が代償分割に該当します。
このように、代償分割は、現物分割が困難な場合に行われる遺産分割の方法です。
③換価分割
換価分割とは、被相続人の遺産を売却等により換価した後に、それによって得られた現金を各相続人に分配する方法を意味します。例えば、被相続人の遺産が土地及び有価証券であり、これらを売却して得られた現金が1億円であった場合、この1億円を各相続人に分配するという分割方法が換価分割に該当します。
換価分割は、上記①の現物分割が困難で、かつ相続人に代償金の支払能力がない場合等の理由で上記②の代償分割も難しい場合に行われる遺産分割の方法です。
④共有分割
共有分割とは、遺産の一部又は全部を各相続人の具体的相続分による物件法上の共有取得とする方法を意味します。例えば、被相続人の遺産に不動産が含まれており、相続人が妻と子の場合、当該不動産について、妻と子がそれぞれ2分の1の共有持分として共有するという分割方法が共有分割に該当します。
なお、このような共有関係を解消するためには、共有者間で共有物分割の協議を行い、協議が調わない場合又は協議ができない場合は共有物分割訴訟(民法258条)の手続が必要となります。
遺産分割の手続と方法の関係
協議分割の場合、相続人が合意する限り、前述の遺産分割方法の①乃至④のいずれも選択することができます。
また、調停分割の場合も、ほとんどの場合において、相続人が合意する限り、①乃至④のいずれの分割方法をも選択することができるとされています。
審判分割の場合、これらの遺産分割方法のうちいずれを選択するかは、家庭裁判所の広い裁量に委ねられています。すなわち、遺産分割の基準として民法906条が「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と規定していることから、家庭裁判所はこれらの事情を考慮して、当事者の意思に拘束されることなく、後見的立場からその裁量権を行使して具体的に決定することになります。
かかる視点からは、まず現物分割を検討し、それが相当でない場合には代償分割を検討し、代償分割もできない場合に換価分割を検討し、共有分割は最後の手段となることになります。
もっとも、実務上は、いずれの遺産分割方法を選択するかを決める際には、各当事者の意向を可能な限り尊重する運用がなされています。
以上
参考文献
第3版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務 片岡武/菅野眞一(編著)
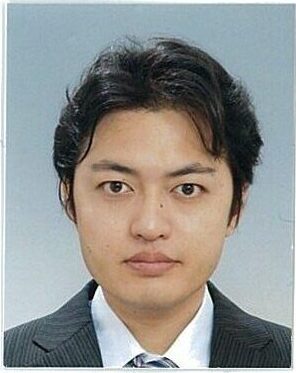

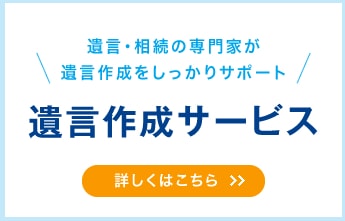
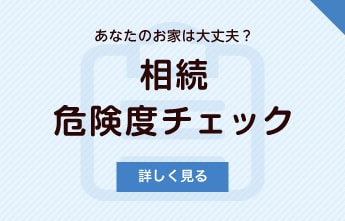
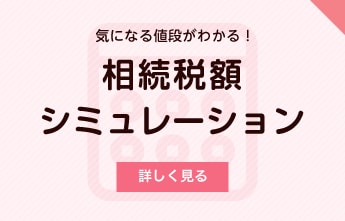

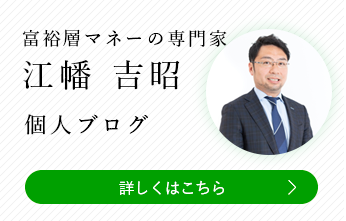
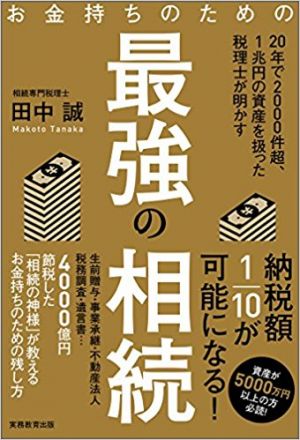
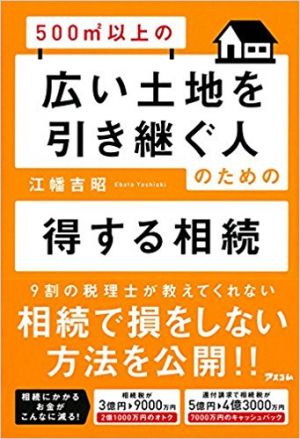
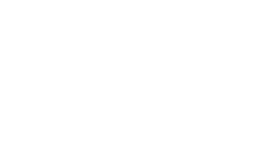 0120-131-554
0120-131-554