
今回は、大規模災害による紛失に備えた遺言の保管についてご説明します。
※本記事と関連する過去の記事
https://egonsouzoku.com/magazine/magazine-374/
https://egonsouzoku.com/magazine/magazine-995/
1 遺言書の紛失・汚損のリスク
遺言書を作成する際には、民法に定められた遺言の方式に関するルールについて内容を確認し、これに従う必要があります。
しかし、定められた方式に基づいて適切に遺言書を作成しても、大規模災害等で遺言書が紛失したり、汚損により判読不能状態になるなど、遺言の内容が実現されなくなるリスクがあります。
そこで、今回は、遺言書の保管についてご説明します。
2 公正証書遺言の保管制度
(1) 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が関与することにより作成される遺言です。
公証人が関与して、法律的な整理がされて作成されることからその有効性が問題になることは少ないというメリットがあります。
(2) 公正証書遺言の保管
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの危険性が少ないことも、公正証書遺言のメリットです。
また、2014年4月1日から、全国の公証役場、公証人において、公正証書遺言の原本を電磁記録化し、原本とは別に保管する、原本の二重保存が実施されています。
したがって、仮に公証役場が被災し、そこで保存されていた公正証書遺言の原本が紛失してしまっても、別に保存されている電磁的記録を利用して原本の復元をすることが可能です。
このように、公正証書遺言については災害による紛失等に備えた安全な保管がされています。
3 自筆証書遺言の保管制度
(1) 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自分で書いて、押印する方式で作成される遺言です。自筆証書遺言は、遺言者本人だけで、特別な費用をかけることなしで、手軽に作成できるというメリットがあります。
(2) 自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言は、多くの場合、自宅で保管されることが多く、紛失、改ざん、汚損等のリスクがあり、自宅が被災した場合に滅失してしまうリスクがあります。
そこで、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)が2020年7月10日に施行され、自筆証書遺言保管制度が運用されています。
遺言者は、一定の手数料を支払い、自ら作成した遺言書の保管の申請をすることができます。ただし、遺言者の意思に基づいて作成・保管されたことを確認するために、遺言者が自ら遺言保管所に出頭してこの申請を行う必要があります。
同制度を利用すると、遺言書の原本は遺言書保管所の施設内で保管され、その画像データも保管されます。
したがって、同制度を利用することで、原本の紛失に備えた安全な保管をすることができます。
4 秘密証書遺言
(1) 秘密証書遺言
普通の方式による遺言として、公正証書遺言、自筆証書遺言とは別に、秘密証書遺言という遺言もあります。
秘密証書遺言とは、遺言が存在することは明らかにしつつも、一定の形式を踏まえることで、その内容を他者に知られないようにするものです。
(2) 秘密証書遺言の保管
自筆証書遺言保管制度の対象は、自筆証書遺言のみです。したがって、同制度を利用して秘密証書遺言を保管することはできません。遺言者は、同制度を利用せずに、秘密証書遺言を保管する必要があり、公正証書遺言及び自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言と比較して、保管の安全性は劣ります。
5 保管制度の適切な利用の重要性
多くの労力と費用をかけて、遺言書を作成しても、災害等によりそれが紛失したり、汚損してしまい、作り直しが必要になることや、遺言の内容が実現されないなどのリスクがあります。
そこで、各遺言の保管方法・制度を理解して、紛失等に備えた適切な保管を検討することが重要です。
※本記事の内容について細心の注意を払っていますが、その正確性及び完全性等の保証をするものではありません。本記事はその利用者に対し法的アドバイスを提供するものではありません。したがって、本記事の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、本ウェブサイトの提供者、本記事の著者及びその他の本記事の関係者は、かかる損害について一切の責任を負うものではありません。


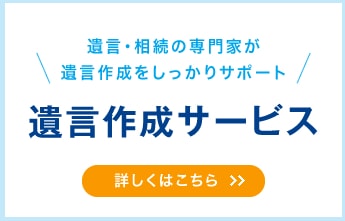
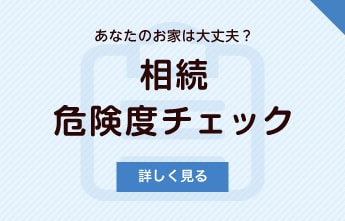
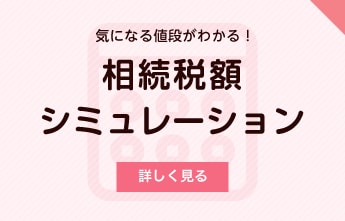

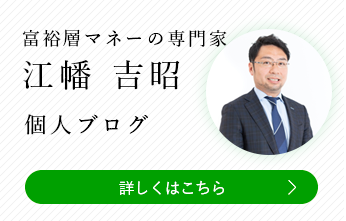
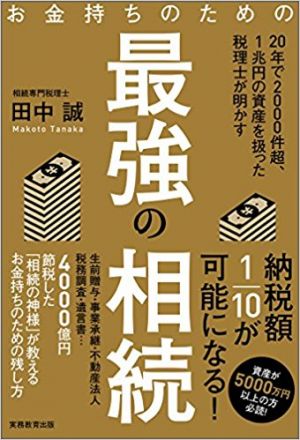
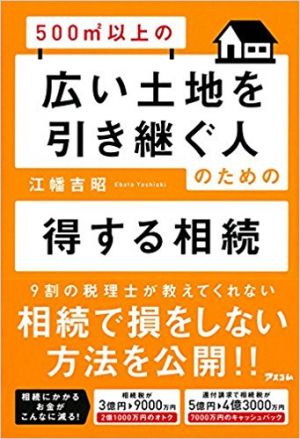
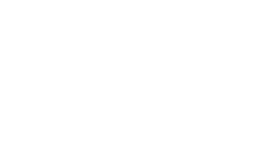 0120-131-554
0120-131-554