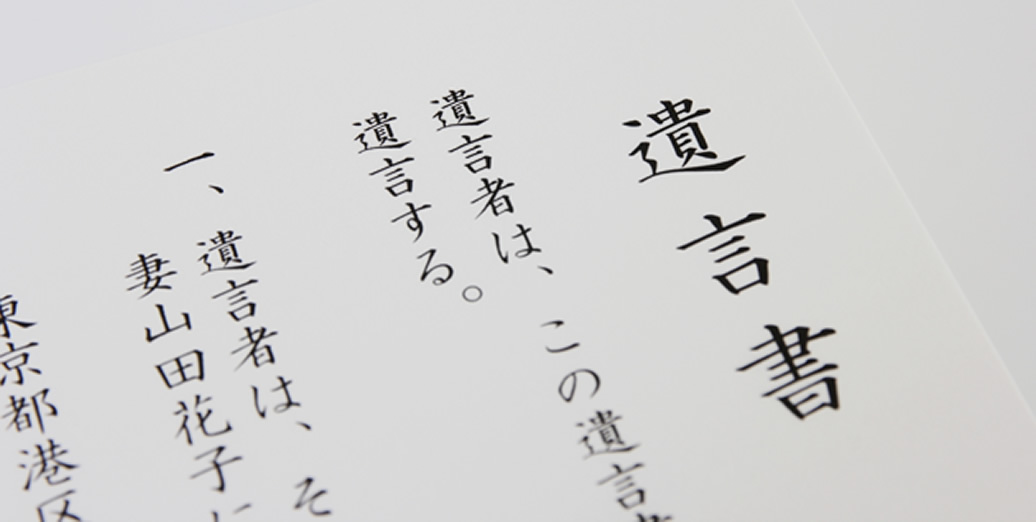
1 相続欠格制度
被相続人の殺害者や遺言書を破棄又は隠匿した者等は、相続人となることができません(民法第891条各号、相続欠格)。
この相続欠格の根拠は、相続秩序の破壊や、被相続人と相続人との間の共同体的結合を破る非行が根拠であると考えられています。
本記事では、同条各号に定められた欠格事由のうち、遺言書の破棄又は隠匿について説明します。
2 要件
「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は、相続人になることができないと定められています(同条第5号)。
まず、同号に該当するためには、被相続人の相続に関する遺言書であること及び被相続人が遺言書を故意に隠匿又は破棄したことが必要です。
さらに、破棄隠匿行為について、単なる故意だけでなく、破棄・隠匿によって不当な利得をする意思が必要であるかについても議論がありますが、不当な利得を目的(たとえば、遺産の帰属を自己に有利する目的等)とするものでなかったときは、相続欠格者に該当しないとされています(最判平成9年1月28日民集51巻1号184頁)。この場合には、遺言に対する著しく不当な干渉行為とはいえず、厳しい制裁を科するのは同号の趣旨に沿わないためです。
また、破棄又は隠匿された遺言書が有効なものである必要があるかについては、議論がありますが、不要である立場とされる裁判例があります(最判昭和56年4月3日 民集35巻3号431頁)。
3 証明・訴訟
遺言書が破棄又は隠匿されたか否かについて紛争になるケースにおいては、上記の要件に該当する事実を直接証明する証拠を確保することが困難であり、遺言者の生前の言動、遺言書の保管場所・方法等に関連する事実を積み上げることによる証明が必要になる場合が多いと考えられます。
当事者間の協議で問題が解決せず、訴訟を提起する場合、共同相続人全員を当事者として、破棄又は隠匿をした行為者について、相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えが必要だとされています(固有必要的共同訴訟、最判平成16年7月16日 民集58巻5号1319頁)。
4 効果
上記の各要件が満たされる場合、当然に相続欠格の効果が発生します。相続開始前の場合には、欠格事由が生じた時点で、相続開始後の場合には、相続開始時にさかのぼって欠格の効力が生じます。
しかし、相続欠格が認められ、行為者が相続から排除されても、遺言書は既に失われてしまっているため、その遺言書に基づく遺言内容を実現することは簡単ではありません。
ただし、被相続人が生前に弁護士に相談しており、弁護士が作成した原稿が存在する等の事情があるケースで、その原稿等に基づく推認により、破棄・隠匿がされた遺言書の内容を確定し、その有効性を認めた裁判例もあります(東京高判平成9年12月15日 判タ987号227頁)。
5 まとめ
一般的に、遺言書の破棄・隠匿が疑われるケースでは、その立証が困難である場合が多く、また、仮に破棄・隠匿が認められ、その行為者が相続から排除されても、その排除のみによって、遺言者が本来意図していた遺言内容を実現することはできません。
そこで、公正証書遺言や遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言を利用する等、破棄・隠匿のリスクを排除することができ、遺言者の意図をより適切に実現できる方法の選択が望ましいと考えられます。
※本記事の内容について細心の注意を払っていますが、その正確性及び完全性等の保証をするものではありません。本記事はその利用者に対し法的アドバイスを提供するものではありません。したがって、本記事の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、本ウェブサイトの提供者、本記事の著者及びその他の本記事の関係者は、かかる損害について一切の責任を負うものではありません。









 0120-131-554
0120-131-554