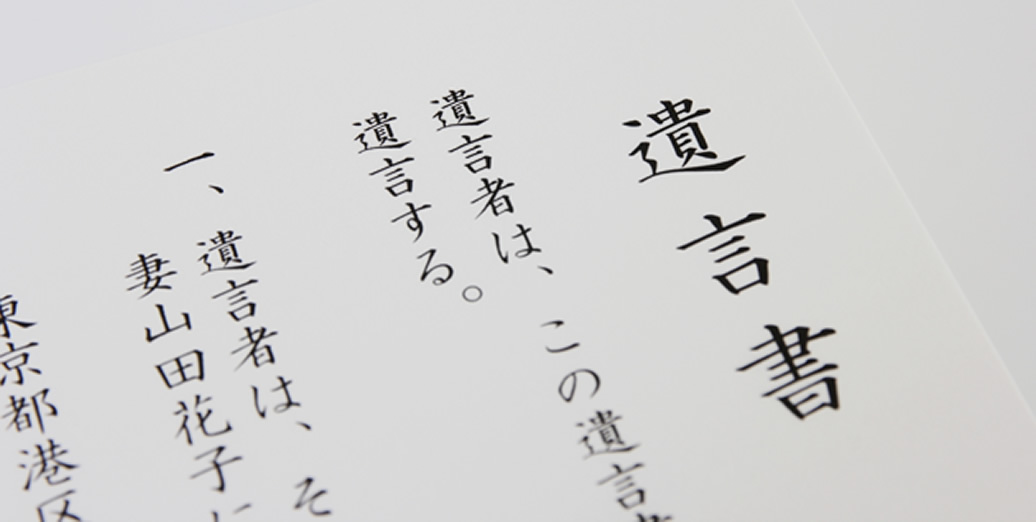
今回は、国際相続として、複数の国が関与する場合の遺言に関してご紹介いたします。
遺言の成立及び効力について
複数の国が関与する場合には、まずは、どこの国の法律が適用されるのかを決める必要があります。その際に適用される法律を準拠法といいます。
遺言においては、法の適用に関する通則法(以下「通則法」といいます。)37条1項によると、遺言の成立及び効力は、遺言成立当時の遺言者の本国法によるとされています。本国法とは、本人が国籍を有する国の法律のことをいいます。また、遺言の成立及び効力の準拠法の基準時は、遺言成立時です。そのため、遺言成立後に、国籍を変更したとしても、準拠法の決定に影響を与えるものではありません。
例えば、遺言成立時に日本国籍を有していた人は、本国法が日本法となりますので、日本の民法によって有効か無効かを判断することになります。
また、遺言の内容(例えば、遺贈や認知など)によっては、通則法37条1項の適用を受けず、相続の準拠法(通則法36条)や認知の準拠法(通則法29条)によって、遺言の成立及び効力がそれぞれ判断されることになります。
遺言の方式
遺言の方式については、通則法の特別法である「遺言の方式の準拠法に関する法律」によることになります。
遺言の方式とは、その外部的形式であり、日本の民法であれば、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言などの方式があります。日本の民法においては、共同遺言(2人以上の者が同一の証書で遺言をすること。)が禁止されていますが(民法975条)、国によっては許される場合もあります。
遺言の方式の準拠法に関する法律では、遺言を方式上なるべく有効と解釈し、遺言を保護するために、遺言は次のいずれかの法で有効とされれば、方式上有効となることが原則となります(遺言の方式の準拠法に関する法律2条)。
①行為地法(法律行為の行なわれる場所の法律のことです。)
②遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
③遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
④遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
⑤不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法のいずれか1つ遺言の方式が適合するとき
例えば、ドイツ国籍を有するAさんが、日本において、遺言書を作成したとします。この場合、準拠法は、ドイツ法となります(通則法37条1項)。また、Aさんが作成した遺言書が、ドイツ法上無効な方式であったとしても、日本の民法上有効となる方式で作成した場合には、遺言の方式については有効となります(上記の①。遺言の方式の準拠法に関する法律2条第1号)。
なお、上記④の「常居所」とは、一般に、人が相当期間、居住することが明らかな地をいいます。そのため、一義的に決定されるわけではなく、居住の期間や経緯、親族の居住地などを総合的に考慮して決することになります。









 0120-131-554
0120-131-554