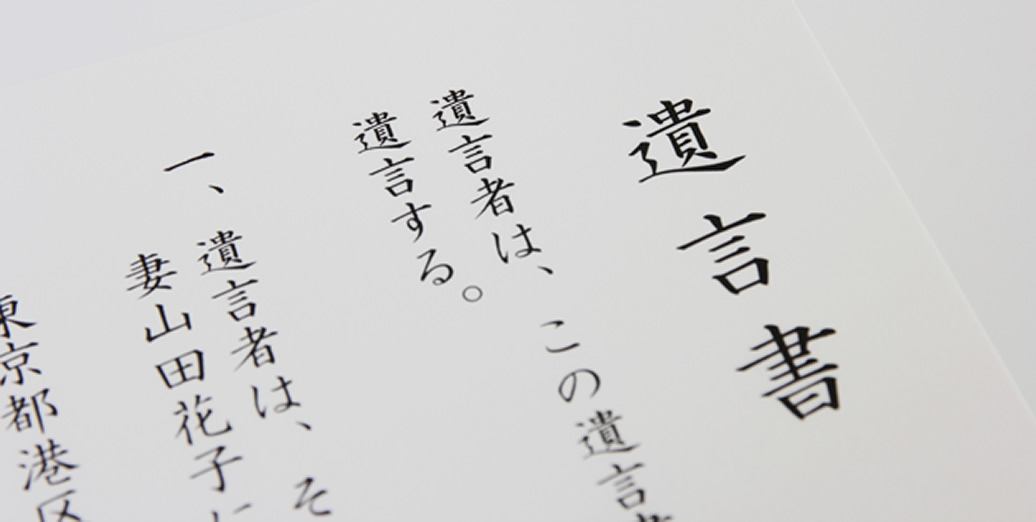
はじめに
前々回は「遺贈」について、前回は「相続分の指定」と「遺産分割方法の指定」の概要についてご紹介しましたが、今回は「相続分の指定」・「遺産分割方法の指定」に加え、「遺贈」という制度を追加して考えてみたいと思います。
【ご参考】遺言相続ドットコムにて、ぜひ改めてご覧ください。
第16回 遺贈(2019.8.6)
第17回 相続分の指定・遺産分割方法の指定①(2019.9.6)
3つのいずれの制度も、遺言者の意思で、“遺産を特定の人物に与えること”を目的としているという点は共通していますが、それぞれ、効果が異なる点があり、その結果、遺言者の予期していたような効果が発生せずに、相続人間で紛争が生じる可能性もあります。
そこで、以下では、「相続分の指定」・「遺産分割方法の指定」・「遺贈」の3つの制度の類似点や相違点を見ていき、ある特定の遺言を具体例として、それぞれの制度の効果としてどのような違いが生じるかについてご説明したいと思います。
「相続分の指定」・「遺産分割方法の指定」・「遺贈」の類似点や相違点とは?
「相続分の指定」や「遺産分割方法の指定」がなされても、相続が開始した時点では効果は発生せず、その後に遺産分割が行われてはじめて、指定を受けた相続人は、当該相続財産の所有権を取得します。
一方で、「遺贈」のうち特定遺贈の場合、受遺者である相続人は、相続開始と同時に、当該相続財産の所有権を取得し、当該財産は遺産分割の対象とはなりません(ただし、財産を取得したこと自体は遺産分割協議において特別受益として考慮されます)。
「相続分の指定」と「遺贈」は、遺留分を侵害しない範囲で、法定相続分を上回っても“相続分を変更する”という点で同じ効果を有します。他方で、法定相続分を下回る場合は「相続分の指定」であれば、指定された相続人は、“その指定された相続分に限って”相続財産の取得が認められるだけですが、「遺贈」であれば、当該相続人の“法定相続分に達するまで”他の相続財産を取得することができます。
また、「遺産分割方法の指定」は、“法定相続分を変更することなく”指定に応じて相続財産を構成する個々の財産を相続人間に帰属させるもので、法定相続分を下回る限り当該相続人の“法定相続分に達するまで”他の相続財産を取得することができるという点で「遺産分割方法の指定」も「遺贈」も差異はありません。
逆に、法定相続分を上回る指定がなされた場合には、遺言者の通常の意思として“法定相続分を変更する”意思、つまり「相続分の指定」の意思も有していると解されます(これを、「相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定」といいます)。
債務(例えば借金)の承継について、相続人は、相続分に応じて被相続人の権利義務を承継することになりますが、この相続分には“指定相続分”も含まれると解されます。したがって、「相続分の指定」があれば、相続人は、プラスの財産だけでなく、相続債務というマイナスの財産も指定された割合に応じて承継することになります(相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定の場合も同様です)。他方、「遺贈」や「遺産分割方法の指定」の場合、その効果として債務を承継するということはありません。
具体例における3つの制度による効果の違いとは?
「相続分の指定」・「遺産分割方法の指定」・「遺贈」は、上記のとおりそれぞれ類似点と相違点を備えています。しかしながら、いざ遺言がなされたとき、3つのうちどの制度に該当するかが不明確な場合もあり、各制度によって結論が異なることもあいまって、紛争の原因にもなりえます。
そこで、以下では具体的な遺言をもとに、各制度を適用した場合の効果の違いや、どこに紛争の原因が生じるかついてご説明します。
いずれの例も、相続人が長男と次男の二人で、遺産として土地(2000万円)、家屋(1000万円)、株式(500万円)、その他預金等の財産(1500万円)で合計5000万円がある場合を想定しています。
⑴「遺産のうち、不動産の3分の1は長男が取得する」という遺言がある場合
この場合、①遺産の総額(5000万円)のうち、不動産の価格(土地と家屋の合計3000万円)の占める割合の3分の1(1000万円)のみを長男の相続分にする「相続分の指定」と解することができる一方で、②遺産のうち、全ての不動産の中の価額の3分の1に相当する特定物の「遺贈」とも解されます。また、③長男に不動産の3分の1が帰属するように遺産分割をするようにという意味で「遺産分割方法の指定」とも解されます。
一見すると、いずれの場合でも最終的に長男が不動産の価格の3分の1に相当する1000万円を取得するという結論に変わりはないようにも見えます。
しかしながら、①の場合、基本的に長男は当該1000万円のみ取得する権利しかありませんが、②・③の場合、1000万円相当を取得することに加えて本来の法定相続分である遺産の2分の1(2500万円)と1000万円の差額である1500万円分についても、取得する権利を有していると解されます。
たとえ、①の場合でも遺産分割協議の中で、長男と次男が納得したうえで、指定された相続分と異なる内容の遺産分割の合意をすることは可能ですが、当事者の一方でも、当該取扱い(解釈)に納得できない場合、紛争に発展しかねません。
具体的には、できるだけ遺産を多く取得したいと考える長男であれば、この遺言を「遺贈」または「遺産分割方法の指定」にあたると主張し、できるだけ遺産を多く取得したいと考える次男であれば、この遺言を「相続分の指定」であると主張しあうことになります。
⑵「長男に家屋を与える」という遺言がある場合
この場合、①長男は家屋だけで満足せよという趣旨であれば「相続分の指定」といえますし、②文言を素直に読めば特定の財産である家屋を長男に取得させる「遺贈」と解されます。他方、③遺産分割に当たり家屋を長男に割り当てよという趣旨であれば、「遺産分割方法の指定」とも解されます。
こちらについても上記⑴と同様に、①と②・③の場合で、長男の取得しうる財産が変わることから紛争に発展する可能性があります。もっとも、当該遺言の場合、②の「遺贈」と解される可能性が高いですので、⑴の具体例と比べて紛争となる可能性は低いとも考えられます。
以上のとおり、一つの遺言がどの制度を意味するかが不明確な場合があり、その結果によって当事者間に重大な利害対立を生む結果にもなり得ます。このような場合、当事者間の協議で解決しなければ、最終的に遺言者の意思がどのようなものであったかを事後的に明らかにして、遺言の意味を確定させることになり、ケースバイケースの判断がされることになります。
今回の解説は、以上です。次回は、本稿でも少し触れた遺言の解釈と相続させる旨の遺言等について見ていきます。

酒井 勝則
東京国際大学教養学部国際関係学科卒、
東京大学法科大学院修了、
ニューヨーク大学Master of Laws(LL.M.)Corporation Law Program修了








 0120-131-554
0120-131-554