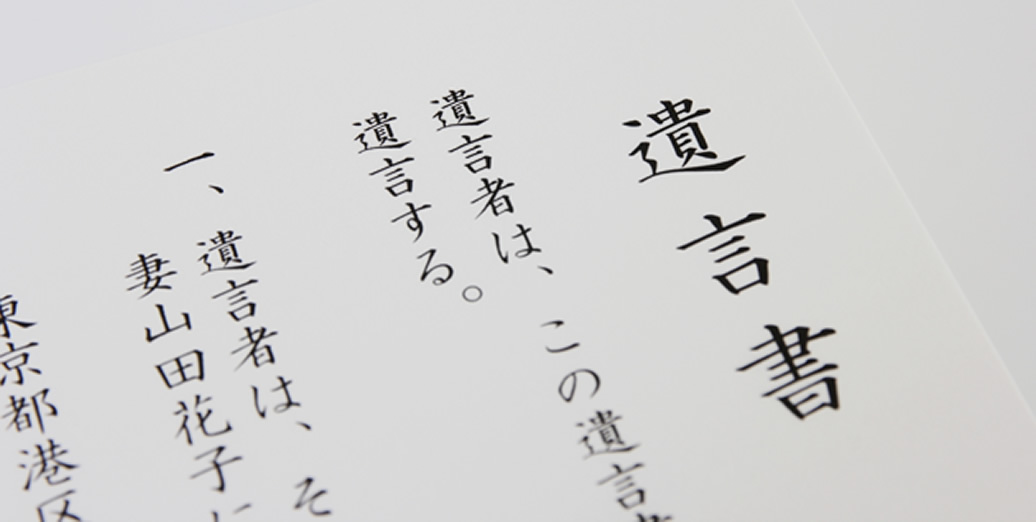
はじめに
今回は、遺言書を偽造、変造、破棄及び隠匿した場合についてご紹介いたします。
まず、民法では以下のとおり規定されており、遺言書を偽造、変造、破棄、又は隠匿した者は、民法891条5号に基づき、相続人となることはできません。
もっとも、遺言書自体を破棄・隠匿するという意思(故意)だけで民法891条5号の要件を充足するのか、それとも、自らが相続法上有利になろうとする意思(故意)までもが必要となるかについては争いがあります。みなさんはどのように考えますでしょうか。ケースを検討しながら、最高裁判決の判断をご紹介いたします。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一~四 (略)
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
ケース
被相続人であるAさんが死亡し、その遺産の全部を共同相続人の1人であるYさんが相続する旨の遺産分割協議(以下「本件遺産分割協議」といいます。)が行われました。
Aさんは、生前Bさんに対して土地(以下「本件土地」といいます。)を売却し、Bさんから本件土地の代金全額を受領していました。また、Aさんは、「Bに売却した土地の売却代金はα社(Yが経営している。)に寄付するから、α社の債務の弁済に充てること」という内容の遺言書(以下「本件遺言書」といいます。本件遺言書は、売買代金債権又は受領した代金相当額をα社に遺贈する趣旨と考えられます。)を残し、Yが本件遺言書を預かりました。
また、本件土地の移転登記は未了のままであったため、共同相続人らは、Bへの移転登記義務をYが責任をもって履行するという趣旨で、Bが本件土地を含めて相続することを承諾し、本件遺産分割協議がなされました。その上で、Yさんは、本件土地についてAさんからの相続登記を経た上で、売買を原因としてBに所有権移転登記を行いました。
ただし、本件遺産分割協議の際、本件遺言書はYのもとには存在せず、所在不明となっていたため、Yは、他の共同相続人に対して、本件遺言書を提示することはできませんでした(なお、平成9年1月28日当時も所在不明でした。)。また、Yは、他の共同相続人に対して、本件遺言書の趣旨・内容を説明するとともに、「右遺言書は、α社の経理担当者であるCが焼き捨てた。」と説明していました(ただし、裁判所は、Yが本件遺言書を破棄・隠蔽したという事実を認定していません)。
その後、共同相続人2名(X1・X2)が原告となり、他のすべての共同相続人(Yを含みます。)及びB(Bは共同相続人ではありません。)を被告として、Yが遺言書を破棄又は隠蔽したため相続欠格者に該当し、同被告が相続権を有しないこと等の確認及び被告ら(Y・B)への移転登記等の抹消登記を求めました。
裁判所における判断
東京高裁では、破棄又は隠匿の事実の存否については判断せず、仮に被告Yが破棄又は隠匿したとしても、遺言書の内容が被告Yに有利なことなどから利得目的(自らが相続法上有利になろうとする意思)が認められず、このような者は相続欠格者に当たらないとして原告らの請求を棄却しました。
最高裁(最判平成9年1月28日・民事判例集51巻1号184頁)では以下のとおり判示し、東京高裁の判断を正当として是認するとしました。
「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法八九一条五号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。けだし、同条五号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにあるが(最高裁昭和五五年(オ)第五九六号同五六年四月三日第二小法廷判決・民集三五巻三号四三一頁参照)、遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、同条五号の趣旨に沿わないからである。」
解説
最高裁判決は、民法891条5号の破棄や隠匿については、遺言書自体を破棄・隠匿するという意思(故意)だけではなく、それによって自らが相続法上有利になろうとする意思(故意)が必要とされることを判示しました。
民法891条5号の趣旨は、遺言に関して著しく不当な干渉行為をした相続人に対して、相続人となる資格を失わせるという非常に厳しい内容の民事上の制裁を課そうとするところにあります。もっとも、最高裁は、同号に当たる相続人の行為が常に遺言に対する著しく不当な干渉行為に当たるとはいえないことを考慮して、遺言書自体を破棄・隠匿するという意思(故意)だけではなく、それによって自らが相続法上有利になろうとする意思(故意)が必要との判断をしました。
なお、本事案においては、そもそも、遺言書自体を破棄・隠匿するという意思(故意)すらなかったのではないかと考えると、最高裁は、自らが相続法上有利になろうとする意思(故意)が必要という判断に立ち入る必要もなかったのではないかという説明もできます。









 0120-131-554
0120-131-554