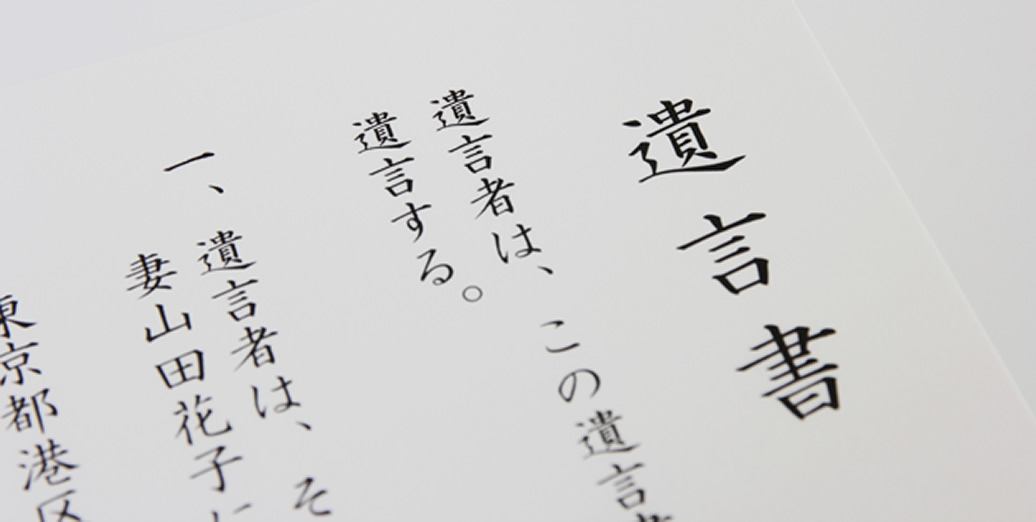
ケーススタディー
現在、Aさんは、資産として、不動産を1件、預貯金を3000万円保有しています。
しかし、Aさんには相続人となり得る人がいません。
そこで、Aさんは、かねてから親交のあったBさん・Cさんに対して、保有している財産を遺言によって譲渡したいと考え、遺言において、Bさんに対しては不動産すべてを、Cさんに対しては預貯金全額を遺贈するとの内容を記しました。
その後、Aさんが亡くなり、遺言書によってBさん、Cさんは財産を譲り受けることになりました。
遺贈の概要
遺贈とは、被相続人が遺言によって他人(受贈者)に、自己の財産を与える処分行為です(民法964条)。簡単にいいますと、上記のケースにおいては、Aさん(被相続人)が、Bさん、Cさん(受贈者)に対して、Aさんが亡くなる前に「Bさん、Cさんに対して自分の財産を与える」という内容の遺言を作成し、その後、Aさんが死亡し、遺言書の効力として一方的に財産を譲渡するというものです。類似の制度として、死因贈与がありますが、死因贈与はあくまで「契約」ですので、双方で合意することが必要ですが、遺贈の場合においては、一方的に譲渡することができます。
遺贈の承認・放棄について
ケースにおいて、BさんがA所有の不動産を譲り受けたくないと考えた場合でも、一方的に譲り受けなければならないのでしょうか。
法律上は、遺贈者(ケースではAさん)が死亡した後であれば、いつでも遺贈を放棄することができます(民法986条1項)。また、遺贈を譲り受けると承認する意思表示や、放棄するとの意思表示は、いったんされると撤回することはできません(民法989条1項)。
もっとも、意思表示に関しては、意思能力がなかったり(民法3条の2)、行為能力が制限されていたり、錯誤・詐欺・強迫を理由とする場合には、取消しをすることができます。
ただし、遺贈の承認・放棄の取消しの行使期間は、追認することができる時から6カ月と短期に限定されていますので、注意が必要です(民法989条2項による919条3項の準用)。
なお、やや発展的ですが、遺贈の承認・放棄については、特定遺贈についてのみ適用されます。理由は、包括遺贈の場合には、相続と同じ扱いとなり、相続放棄に準じて取り扱われるべきだからです。
遺贈の無効・取消について
ケースにおいて、遺言書として法律上要求されている要件を満たしていない場合は、遺贈はどうなるのでしょうか。
遺贈は、遺言によってされるものですので、遺贈について記載された遺言書が法律上要求されている要件を満たしていない場合には、遺言自体が無効となりますので、遺贈も無効となります。また、遺贈特有の無効事由に該当する場合にも無効となりえます。具体的には、①遺言者(Aさん)が死亡する以前に(同時に死亡する場合も含みます。)、受贈者(Bさん・Cさん)が死亡した場合(民法994条1項)、②Aさんが、「Bさんの孫が生まれたときは、不動産を遺贈する」などのような条件を設定した場合において(停止条件付き遺贈といいます。)、条件が成就する前にBさん(受贈者)が死亡した場合(同条2項本文)、③遺贈の目的である権利が、Aさん(遺言者)の死亡時点で相続財産に属していなかった場合(民法996条)において、遺贈も無効となります。
また、遺贈がなんらかの理由で無効となった場合や、遺贈の放棄によって失効した場合、基本的には、受贈者(Bさん・Cさん)が譲り受けるはずだった財産は、相続人に帰属します(民法995条)。しかし、ケースにおいては、相続人がいませんので、相続財産は法人とされ(民法951条)、相続財産管理人が選任され(民法952条)、相続財産の清算が行われます(民法957条)。清算後、なお残余財産が存在する場合には、特別縁故者(内縁の配偶者・事実上の養子・献身的な世話をした隣人・生活資金、事業資産を援助してきた者などをいいます。)に対する分与の制度を経て、国庫に帰属します(民法959条、同法958条の3)。
なお、特別縁故者についてですが、誰が特別縁故者(民法958条の3)に該当するか、どの遺産を、どれだけ分与させるかどうかは、家庭裁判所の裁量により判断されます。そのため、既に挙げている特別縁故者の例に該当することをもって、特別縁故者に該当するとは限りません。特別縁故者に該当することから財産分与して欲しいという方は、管轄している家庭裁判所に対して、家事審判申立書を提出することになります。









 0120-131-554
0120-131-554