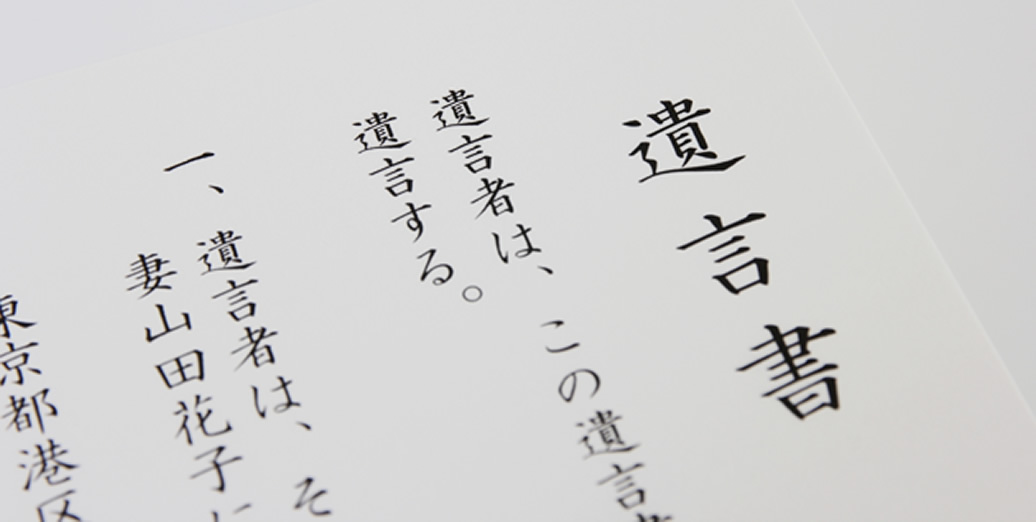
前回に続き、遺留分制度についてご紹介します。
ケース(事件の概要)
令和3年2月1日に、Aさんが亡くなりました。Aさんの相続人は、妻のYさん、3人の子供(X1さん(長女)、X2(長男)、X3(次女))です。また、Aさんの生前の財産は、1億2000万円の現金のみで、負債などは特にありません。令和3年2月7日、Aさんが亡くなる前に「すべての財産を妻に相続させる。」との遺言を残していたことが発覚しました。この場合において、子ども3人は一切、財産を取得できないのでしょうか。
<ケース1>
ケースの場合において、Aさんが、令和2年10月31日、知り合いのBさんに、3600万円の現金を贈与していた場合にはどうなるでしょうか。
結論としては、X1さん(長女)、X2(長男)、X3(次女)は、1300万円ずつ請求することができます。請求の相手としては、Yさんになります。
まず、遺留分制度において、取得できる金額は、前回「第35回遺留分制度について(その①)」で解説したとおり、二段階になっていて、まずは、①遺留分の権利を有する人全員が総額でどの程度までの財産を受け取ることができるかを決めて(民法1042条1項、1043条1項)、②その決まった総額を、各個人にどの程度分配するのかを決めるという(民法1042条2項、900条)方式をとっています。
今回、問題となるのはその①についてです。①の基礎となる財産を「遺留分を算定するための財産の価額」(民法1043条1項)といい、基礎財産と呼ぶことにします。基礎財産は、死亡した人(本件では、Aさん)が相続開始時点(通常は、死亡時)で有していた財産(遺贈財産を含みます。)+(贈与した財産)-(相続債務の全額)で計算できます(民法1043条1項)。
また、(贈与した財産)は、基本的には、相続開始前の1年間にした贈与、つまり、本件では、Aさんが死亡した時点から1年前までの間に行われた贈与については、含まれることになります(民法1044条1項前段)。
本件においては、Aさんの死亡日時は、令和3年2月1日であり、知り合いのBさんには、令和2年10月31日において、3600万円の現金を贈与しておりますので、一年以内といえます。
したがって、3600万円の贈与は基礎財産に含まれることになります。また、基礎財産の合計は、1億2000万円+3600万円で、1億5600万円となります。
次に、今回のケースでは、①遺留分を有する人全体でもらえる財産は、財産の2分の1となります(民法1042条1項2号)。そのため、総額は、7800万円です。また、②についても、妻の相続分が、1/2であり、残りを子どもが取得することになりますが、3人いるので、1/2×1/3=1/6という計算になります。
よって、子どもX1、X2、X3は、それぞれ1300万円を、取得することができます。
なお、遺留分を請求する相手ですが、遺言によって財産を取得する受遺者(Y)と贈与によって財産を取得する受贈者(B)の両者が存在する場合には、受遺者が先に負担する(民法1047条1項1号)と定められておりますので、今回のケースでは、Bではなく、Yに対して請求することになります。
<ケース2>
ケースの場合において、Aさんは、現金の他に不動産をもっており、Aさんは友人であるCさんに対して、「私が、死んだことを条件に不動産を贈与する」ということを約束し、その内容の契約書があった場合にはどうなるでしょうか。
結論としては、贈与した不動産も基礎財産に含まれ、不動産の価格に応じて、Y又はCに対して、請求することができます。
遺留分制度において、取得できる金額は、前記のとおり、二段階です。
ケース2についても、①における基礎財産に含まれるかどうかが問題となります。基礎財産には前記のとおり、死亡した人(本件では、Aさん)が相続開始時点(通常は、死亡時)で有していた財産(遺贈財産を含みます。)+(贈与した財産)-(相続債務の全額)で計算されます。
今回は、「私が、死んだことを条件に不動産を贈与する」との内容で、死因贈与と呼ばれるものであり、遺贈財産に含まれると考えるのが一般的です。
そのため、Cに贈与した不動産も、基礎財産に含まれます。また、不動産などは、金銭換算して計算するのですが、不動産の価値の基準日は、相続開始時点つまり、Aの死亡時点となります。その時点における、不動産の価値を計算し、他のケースと同様に計算を行います。
<ケース3>
ケースの場合において、Aさんが有していた1億2000万円の他に、死亡保険の受取人としてYさんが指定されていた場合についてはどうなるでしょうか。
結論としては、死亡保険は、基礎財産に含まれず、遺留分制度においては考慮されません。
遺留分制度において、取得できる金額は、前記のとおり、二段階です。
ケース3についても、①における基礎財産に含まれるかどうかが問題となります。しかし、死亡保険などの場合、第三者を受取人として指定している保険金については、受取人固有の権利であり、受取人の財産とされ、死亡した人の財産とは考えず「被相続人が相続開始時点で有していた財産」(民法1043条1項)には含まれないとするのが、裁判所の考え方です。
<ケース4>
ケースの場合において、「すべての財産を妻に相続させる。」でありましたが、妻ではなく「すべての財産をDに相続させる。」であった場合には、妻Yも遺留分の請求をすることができるでしょうか。
結論としては、Yも請求することができます。
遺留分の権利は、すべての相続人に与えられているわけではなく、兄弟姉妹以外の相続人、具体的には、配偶者、子ども、亡くなった方のご両親など(正確には、「直系尊属」といいます。)に限定されています。
したがって、妻も請求することが可能です。
ケースや、ケース1、2などで、Yが請求することができなかったのは、Yは遺留分制度において取得できる金額以上を、相続によって取得していたためです。今回は、すべてDに相続させるとのことですので、Yは請求することができます。
なお、子及び配偶者が法定相続人である場合の配偶者の法定相続分は2分の1(民法900条1号)ですので、妻であるYの遺留分は、遺留分を有する人全体でもらえる財産の2分の1、すなわち基礎財産の4分の1となります。
<ケース5>
ケースの場合において、X1、X2、X3さんが、Yに対して、遺留分の請求をしたのが、Aが死亡した令和3年2月1日から、3年が経過した令和6年2月20日である場合はどうなるでしょうか。
結論としては、時効により遺留分侵害額の請求ができなくなる可能性が高いです。
遺留分制度においては、相続開始(本件では、Aが死亡した時点です)、および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって遺留分侵害額の請求権は消滅します(民法1048条)。
したがって、ケース5では、X1、X2、X3が、Aが死亡したことを知り、Aさんが亡くなる前に、「すべての財産を妻に相続させる。」との遺言を残していたことを知ってから、1年以内に請求する必要があります。しかし、X1、X2、X3が請求したのは、3年が経過した令和6年2月20日でありますので、遺言の存在を知らなかったなどの特別な事情がない限り、時効が完成している可能性が高いです。
<ご参考>
上記で引用した民法の条文は、以下のとおりです。
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 略
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 略
3 略
(受遺者又は受贈者の負担額)
第千四十七条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 略
三 略
2 略
3 略
4 略
5 略
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。









 0120-131-554
0120-131-554