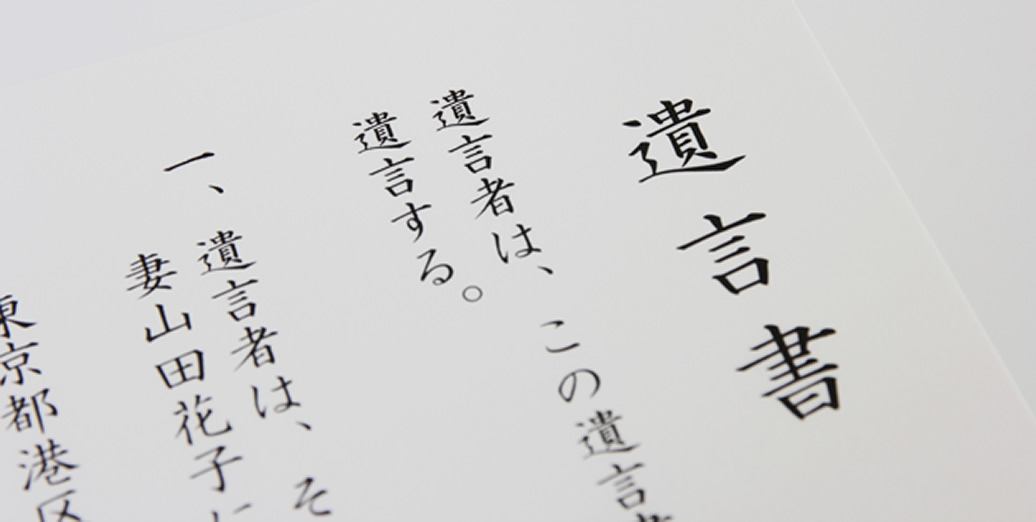
遺贈とは
前回、遺言の撤回についてご紹介しましたが、今回は、遺贈についてご紹介します。
遺贈とは、遺言によって財産を他人に無償で与える行為をいいます。
被相続人が、遺言をすることなく亡くなると、民法上の定めにしたがって相続人が法定相続分を相続する権利を取得しますが、被相続人(遺言者)が、特定の相続人や相続人以外の人(株式会社などの「法人」も含みます)に財産を与えたい場合や、民法上定められた割合と異なる相続分を与えたい場合などには、遺贈による必要があります。遺贈によって利益を受ける人を「受遺者」、相続人など遺贈を実行すべき義務を負う人を「遺贈義務者」といいます。
遺贈には、大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、条件・期限を付けたものや負担を課した遺贈もあります。また、遺贈に類似の制度として、死因贈与というものもあります。以下では、さまざまな遺贈の性質や、死因贈与との相違点について解説していきます。
「包括遺贈」と「特定遺贈」とは?
遺贈に関する民法上の規定は、以下のとおりです。
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
上記のとおり、遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
包括遺贈とは、遺産の全部または割合で示された一部を遺贈する場合のことをいいます。例えば、「私は、私の財産の全部(又はその一定の割合)を内縁の妻であるAに包括して遺贈する。」というものがこれにあたります。
他方、「特定遺贈」とは、その名のとおり、特定の財産を遺贈する場合のことをいいます。例えば、「私の所有する別紙不動産目録記載の土地を内縁の妻であるAに遺贈する。」というものがこれに当たります。
「包括遺贈」に特有の性質とは?
包括遺贈の受遺者(「包括受遺者」といいます。)は、遺贈の効力発生つまり遺言者が死亡すると同時に、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も承継することになります。この点で、相続人も、被相続人の死亡と同時にプラスとマイナスの両方の財産を承継することから、相続人と包括受遺者の地位は類似することになります。そこで、民法は、包括受遺者が相続人と同一の権利義務を有する旨を定めています。
(包括受遺者の権利義務)
第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
包括受遺者は、相続人と同様に、自己のために包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、遺贈を放棄することができます。放棄に期間制限が付されている点で、後述する特定遺贈とは異なります。
「特定遺贈」に特有の性質とは?
特定遺贈の対象となる財産は、土地・建物といった特定物に限られず、牛20頭のうち10頭といった不特定物でも、一定額の金銭でもかまいません。また、受遺者が遺言者に対して負う債務(例えば、借金)を遺言で免除する場合も、特定遺贈に当たります。
特定物の遺贈の場合、遺贈の効力が発生すると同時に、当該特定物の所有権は、遺言者から受遺者に直接移転します。この時、土地や建物といった不動産を遺贈された受遺者は、確定的に所有権を確保するために、登記をしておく必要があります。
また、特定遺贈の受遺者は、いつでも遺贈を放棄することができ、放棄の意思表示をすることで、遺言者の死亡時に遡って遺贈の効力は消滅します。
(遺贈の放棄)
第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
遺贈は、後述する死因贈与とは異なり、単独行為つまり受遺者の承諾なく効力が発生します。遺贈は、無償の財産の譲渡なので、受遺者にとって基本的に利益となりますが、それでも受遺者の意思に関わりなく強制的に財産を帰属させることは受遺者にとって不都合な場合もあると考えられたために、放棄することが認められています。受遺者が、遺贈義務者に対して、承認の意思表示をすると、遺贈の効力は確定し、放棄はできなくなります。
条件・期限付遺贈、負担付遺贈とは?
遺言者は、特定遺贈又は包括遺贈をするにあたり、その効力の発生について、実現の不確実な事実にかからせることができ、これを「停止条件付遺贈」といいます。例えば、「孫であるAが結婚したら自宅不動産を遺贈する。」というものです。
条件ではなく始期や終期を定めた「期限付遺贈」というものもあります。例えば、「私が死んで1周忌が来たら、Aに土地を遺贈する」というものです(始期付遺贈)。
また、遺言者が、受遺者に一定の義務を課す特定遺贈や包括遺贈を「負担付遺贈」といいます。負担の履行によって利益を得る人を「受益者」といいます。例えば、「私の妻Aに300万円を与える。その代わり、Aは私の父Bを扶養すること。」などが考えられます。ここでの負担は、受遺者の行為を内容としますが、違法な行為や法律上強制することができない行為(例えば、「再婚しないこと」など)を内容とする負担は、無効となり、遺贈の効力自体が無効となる場合もあります。負担付遺贈の場合でも、遺贈の効力自体は、遺言者の死亡によって生じ、負担が履行されたかどうかは、遺贈の効力に影響しません。その代わりに、遺言者の相続人や遺言執行者、受益者は、受遺者に対して、相当の期間を定めて負担の履行請求をすることができ、期間内に負担の履行がされない場合には、家庭裁判所に負担付遺贈の取消しを請求することができます(民法第千二十七条)。
遺贈と死因贈与の違いは?
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与のことをいいます。一方当事者の死後の財産処分という点で遺贈と共通するため、死因贈与には、「その性質に反しない限り」、遺贈に関する規定が準用されます(民法第五百五十四条)。その結果、死因贈与の贈与者は、いつでも死因贈与の全部又は一部を撤回することができます。ただし、前述の負担付遺贈に類似する負担付死因贈与(例えば“生前中に〇〇をしてくれたら財産を与える”といったもの)で、受贈者が負担を履行した場合には、受贈者の期待を尊重して、贈与者による撤回は認められないとされています。
死因贈与は、民法上の贈与契約の一種ですので、当事者間の合意が必要となり、遺言者の一方的な意思表示のみで効力が発生する遺贈とは異なります。
次回は、遺贈と関連性のある遺産分割方法の指定について検討します。

酒井 勝則
東京国際大学教養学部国際関係学科卒、
東京大学法科大学院修了、
ニューヨーク大学Master of Laws(LL.M.)Corporation Law Program修了








 0120-131-554
0120-131-554