
はじめに
前回に続いて、遺産分割における諸問題についてのまとめ解説の第3回目となります。
今回も遺産分割の対象となる財産に該当するか否かについて、具体的にご説明いたします。
具体的検討(前回からの続き)
(4) 預貯金以外の金銭債権×
被相続人の損害賠償請求権や賃料債権等の金銭債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、よって遺産分割の対象財産に該当せず、相続人間で遺産分割の対象に含める旨の合意があった場合に限り、例外的に遺産分割の対象とすることができるとされています。
前回、預貯金債権の説明において引用した平成28年12月19日の最高裁判決が下されるまでは、預貯金債権も含め上記のように解されていましが、この最高裁判決以降、預貯金債権については、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されず、遺産分割の対象となります。もっとも、それ以外の金銭債権については、従前のとおり、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、相続人間の合意がない限り遺産分割の対象とはならないことになります。
(5) 動産・現金〇
被相続人が所有していた動産類も当然に相続財産に含まれ、共同相続人の共有物として遺産分割の対象となります。
また、現金も動産であるため、動産と同様に遺産分割の対象となることに争いはありません。
(6) 株式〇
株式は、株主がその株主たる資格にもとづいて会社に対して有する法律上の地位と解されています。よって、相続人は相続によりそのような法律上の地位を承継することになり、相続財産に含まれることに争いはありません。
遺産分割の対象となるか否かについては、株主の権利は、株主たる地位に基づいて、剰余金の配当を受ける権利等のいわゆる自益権と、株主総会における議決権等のいわゆる共益権を含む株主の会社に対する法的地位であることに鑑みれば、株式は不可分であり、よって相続開始と同時に相続分に応じて当然には分割されず、遺産分割の対象となるとされています。
(7) 社債〇
社債は、社債権者と社債を発行した会社との間の社債契約という金銭消費貸借契約に類似する契約と解されています。よって、社債の相続人は相続によりそのような契約上の地位を承継することになり、相続財産に含まれることに争いはありません。
遺産分割の対象となるか否かについては、会社法が、社債原簿の記載変更等の請求を相続人の共同で行わなければならないと規定していること、及び社債権者集会における議決権が認められることに鑑みれば、株式と同様に社債も相続開始と同時に相続分に応じて当然には分割されず、遺産分割の対象となるとされています。
(8) 国債〇
国債は、国が歳入の不足を補う目的で国債購入者から金銭を借り入れることによって負担する債務であり、国債購入者と国との間の国債契約という金銭消費貸借契約に類似する契約と解されています。よって、国債の相続人は相続によりそのような契約上の地位を承継することになり、相続財産に含まれることに争いはありません。
遺産分割の対象になるか否かについては、国債については法令で購入単位が定められており、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されれば、かかる法令の趣旨を害することになりますので、相続開始と同時に相続分に応じて当然には分割されず、遺産分割の対象となるとされています。
以上
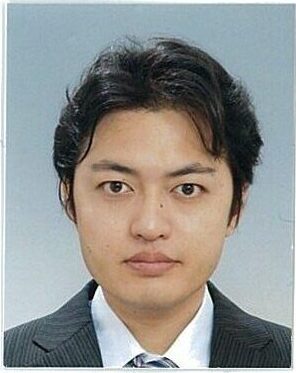

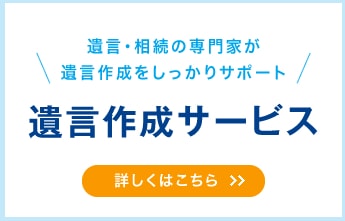
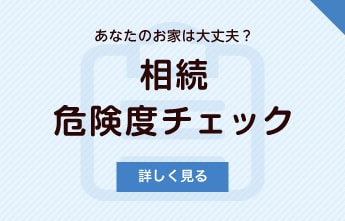
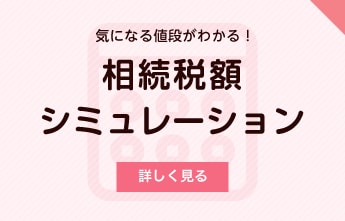

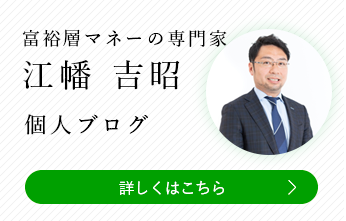
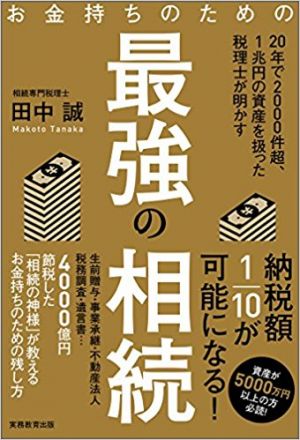
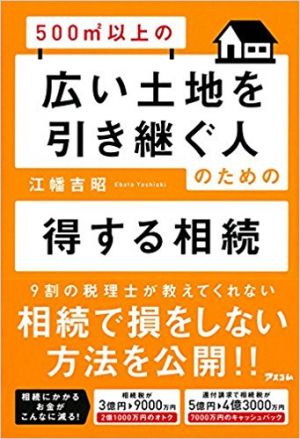
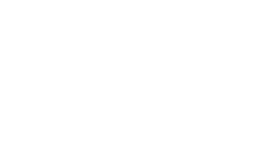 0120-131-554
0120-131-554